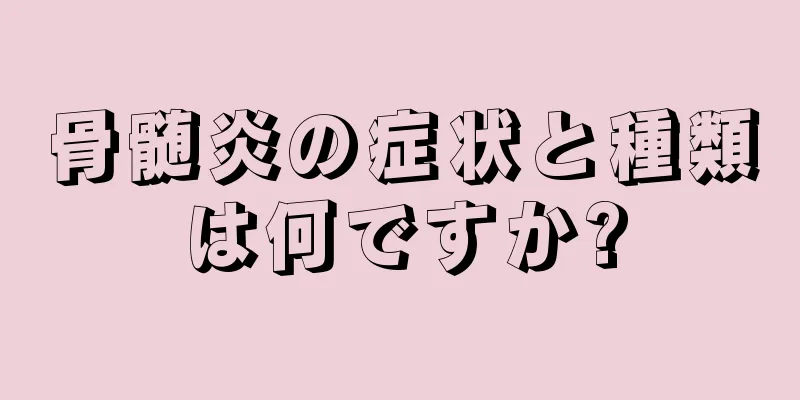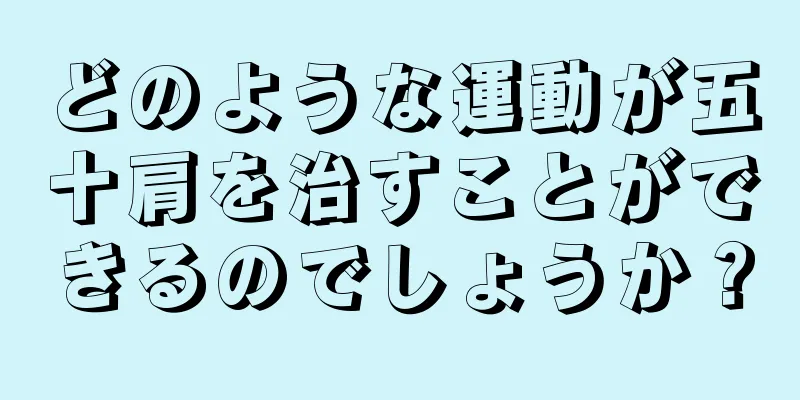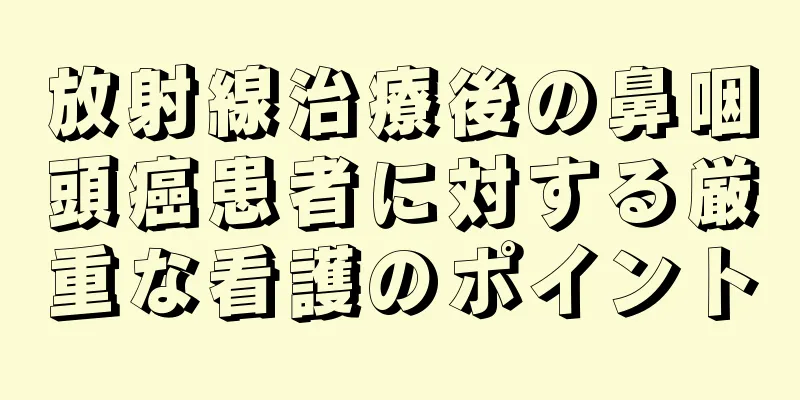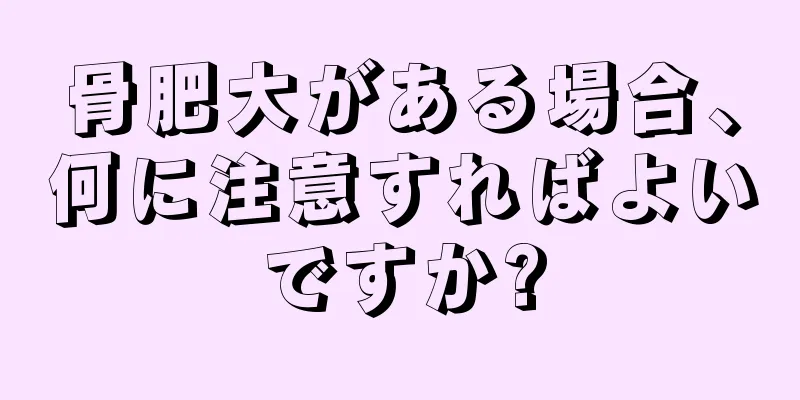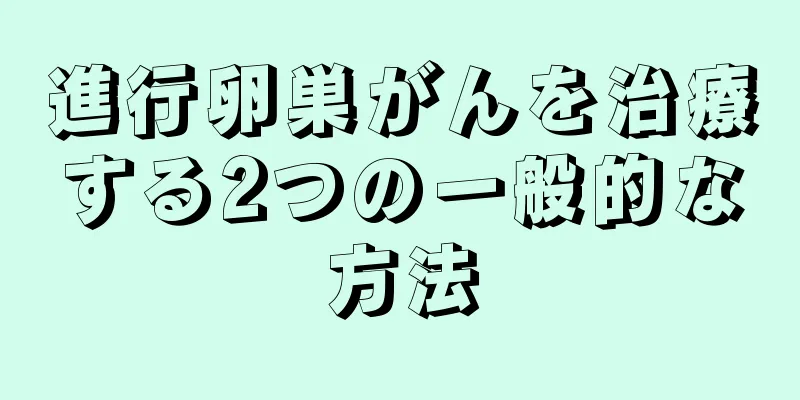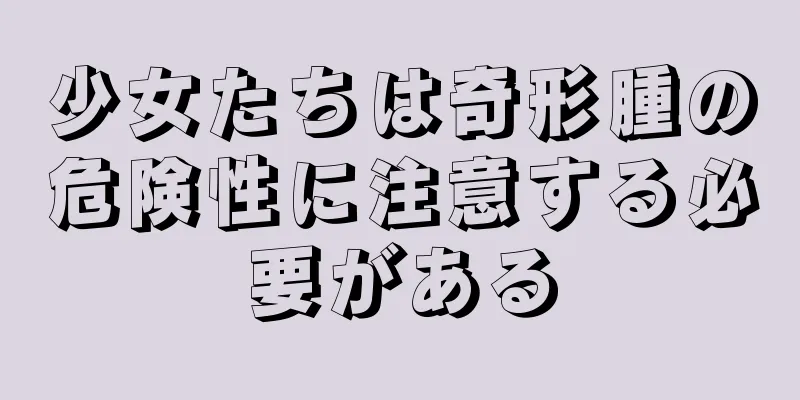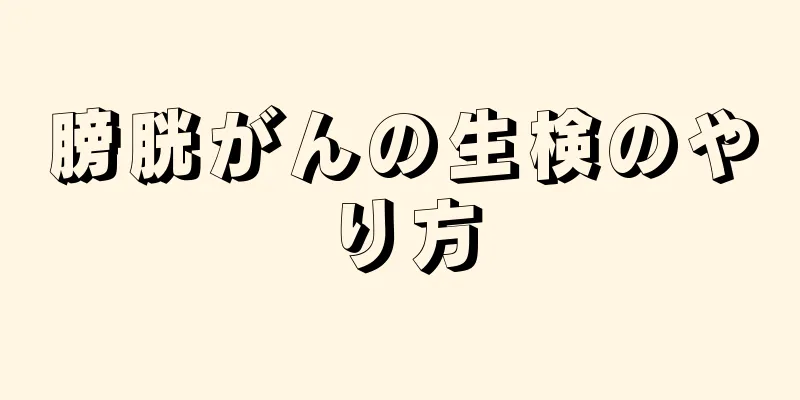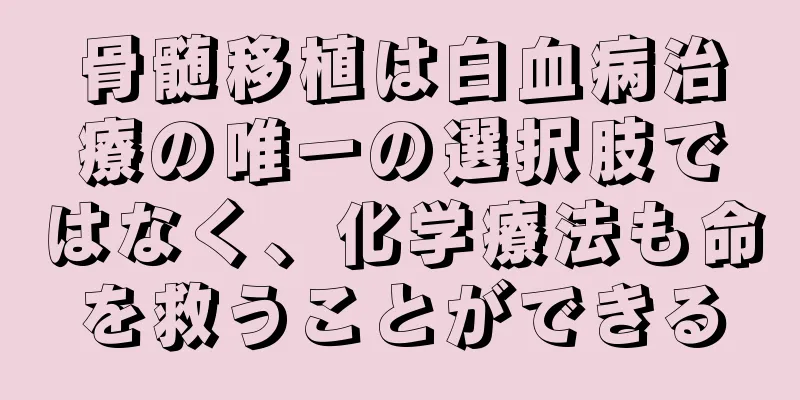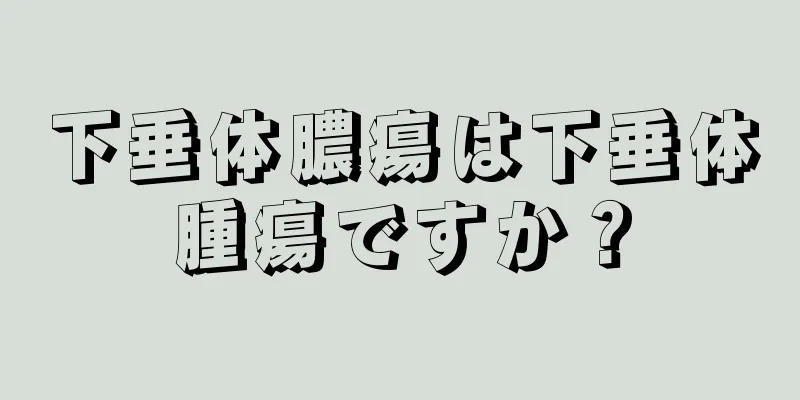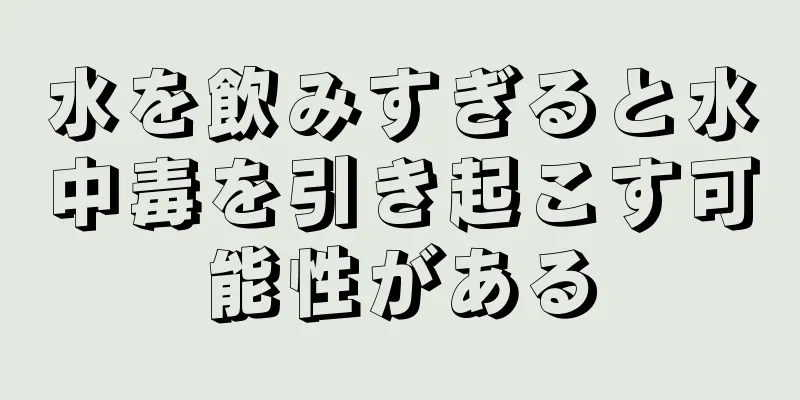発芽後に食べられなくなる食べ物は何ですか?
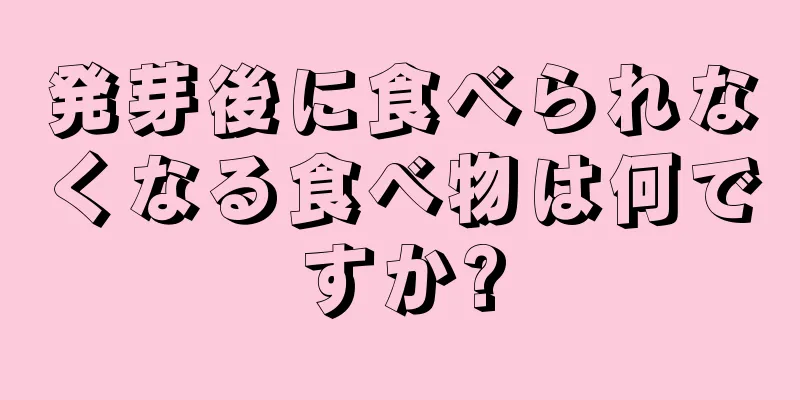
|
春はあらゆるものが育つ季節です。農作物だけでなく、家庭で育てている野菜もすくすくと育ちます。数日間食べないと野菜に芽が出ることに気づく人は多いでしょう。それで、これらの野菜は現時点ではまだ食べられるのでしょうか?これらの発芽食品を食べると中毒を引き起こしますか?この質問は、実際には野菜の種類に基づいて検討する必要があります。 芽が出た後に絶対に食べてはいけないもの:ジャガイモ 芽が出たジャガイモは、食中毒を引き起こす可能性のある一般的な食品の1つです。済南大学付属第一病院健康管理センターの副主任医師である陳祖輝氏は、以前のインタビューで、ジャガイモ自体に有毒なアルカロイドのソラニンが含まれていると述べました。ジャガイモが芽を出すと、この物質の濃度が大幅に増加し、摂取後に中毒を引き起こす可能性があります。 「未熟で緑や紫の部分があるジャガイモや、芽が出たジャガイモにはソラニンが多く含まれています。少量でも食べると食中毒になり、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱などの症状が出ます。この時は、嘔吐や下剤による応急処置が必要です。重症の場合は、病院で胃洗浄、浣腸、下剤などの治療を受ける必要があります。」 発芽は栄養と味に影響します:ショウガ、サトイモ、タマネギ、サツマイモ ショウガ、サトイモ、タマネギ、サツマイモは塊茎を持つ野菜なので、春に芽を出すのはとても簡単です。これら4つの食品は、ジャガイモとは異なり、発芽後に毒素を生成することはありませんが、発芽によりこれらの食品の栄養素が消費され、水分が失われます。そのため、これら4つの食品は発芽後も食べることができますが、栄養価と味は大幅に低下します。 春の湿気の多い気候は、これら4種類の食品を腐らせたりカビを生えさせたりすることがあり、高温調理でも除去できない人体に有害なさまざまな毒素を生成することにも注意が必要です。健康のために、腐敗やカビを見つけた場合は、すぐに捨ててください。 発芽後に栄養価が増す:緑豆、大豆、エンドウ豆、ピーナッツ 実は、発芽後にすべての食品に悪影響が出るわけではありません。私たちがよく食べるもやしや豆苗は、実はもやしからできた製品なのです。 緑豆、大豆、エンドウ豆は発芽すると、もやし、大豆もやし、エンドウ豆もやしなどの身近な野菜になり、豆とは全く違う味で、また、他の異なる栄養価ももたらします。 例えば、大豆の芽には大豆よりも多くのタンパク質、イソフラボン、ビタミン C が含まれており、消化されやすいです。一方、エンドウ豆の芽にはカロチンが豊富に含まれています。ピーナッツの芽も近年非常に人気のある野菜です。ビタミンCが豊富で、レスベラトロールやフラボノイドなどの抗酸化物質が含まれています。 ただし、もやしなどの野菜は一般的に専門的に栽培する必要があることに注意してください。不適切な保管により自宅で芽が出た場合、腐敗やカビが発生することが多く、現時点で食べるのはコストに見合わない可能性があります。 この記事は医師に次のことを指示します。
|
推薦する
オレンジの皮の効果 オレンジの皮の効果
オレンジの皮の効能: 1. 脾臓虚弱、食欲不振、消化不良、吐き気、嘔吐に用いられる本品は湿を乾かし、...
前立腺がんの早期診断は、以下の点に基づいて行うことができます。
前立腺がんを正しく診断するためには、前立腺がんの早期診断を知ることが重要です。では、前立腺がんの早期...
患者は腰の筋肉の緊張に対する健康運動を学ぶべきである
腰の筋肉の緊張は患者に多大な痛みをもたらします。なぜなら、この病気にかかった後、患者は通常通り働くこ...
肛門ポリープの入院費用は高いですか?
肛門ポリープの入院費用は高いですか?肛門ポリープについては誰もが聞いたことがあるはずです。この病気は...
乳がんの初期症状は治癒できますか?
早期乳がんは治癒できますか?これは、多くの早期乳がん患者とその家族が非常に心配している質問であり、多...
気管支炎の食事療法7つ
生姜茶:生姜を洗って10枚に切り、茶葉7グラムを加えて煮出してジュースにして飲みます。発汗を促し、外...
くる病は遺伝性ですか?真実はこうだ
くる病の正式名称はビタミンD欠乏性くる病で、慢性的な栄養欠乏症です。ではくる病は遺伝するのでしょうか...
副腎腫瘍の原因は何ですか?
副腎腫瘍を引き起こす要因は何ですか?病気の発生には理由があります。病気の原因を理解すれば、予防でも治...
5種類の「小雪」健康維持薬膳
冬が近づくにつれて気温の変化が大きく、特に「小雪」の節気を過ぎると気温が急激に下がります。伝統的な中...
外痔核を予防する方法
外痔核はもはや私たちにとって珍しい病気ではありません。その発生は患者の健康に深刻な影響を及ぼします。...
滑膜炎に関連する健康問題
滑膜炎は一般的な整形外科疾患であり、多発性疾患です。病気の主な発生部位は膝関節です。なぜなら、膝関節...
半月板損傷の外科的治療
ひどく損傷した半月板は長い期間にわたって変性し、関節軟骨にひどい摩耗や裂傷を引き起こしたり、関節に明...
胆石を正しく診断する
胆石があるかどうかを診断する正しい方法は何ですか?病気の治療が効果的かどうかは、治療前の患者の診断が...
胆嚢がん患者は日常生活でのケアに注意を払う必要がある
胆嚢がんの発生は主に食事要因によって引き起こされます。胆嚢がんの発生は早期に抑制する必要があります。...
尿路結石をどのように見分けるのでしょうか?
人生には似たような症状を示す病気がたくさんあります。区別の仕方がわからないと誤診が起きやすくなります...