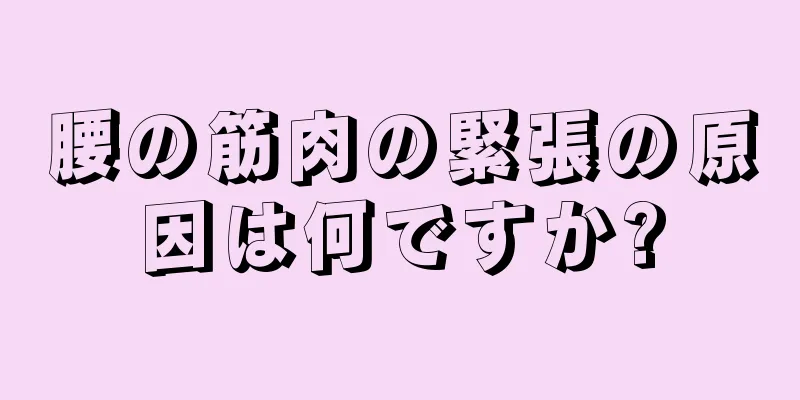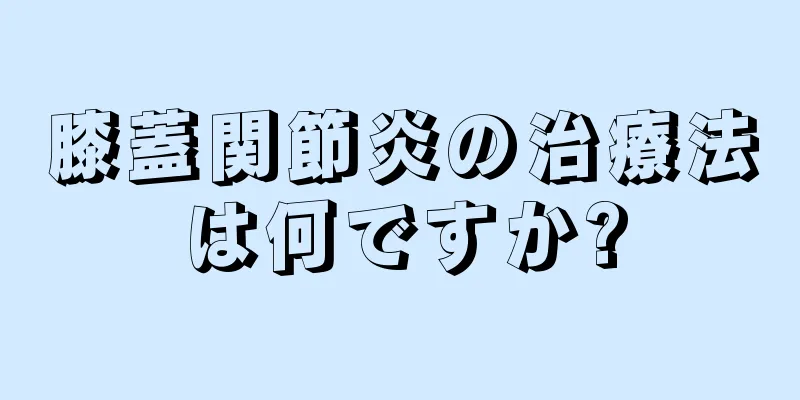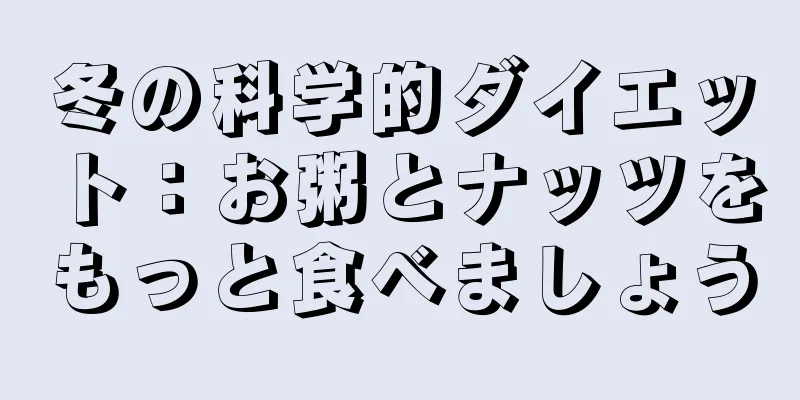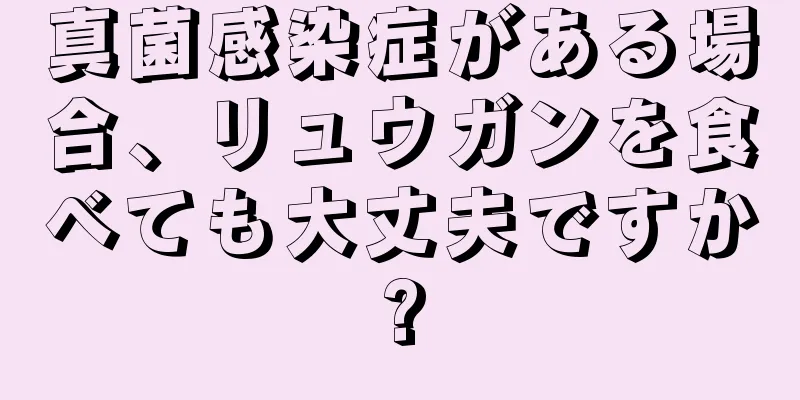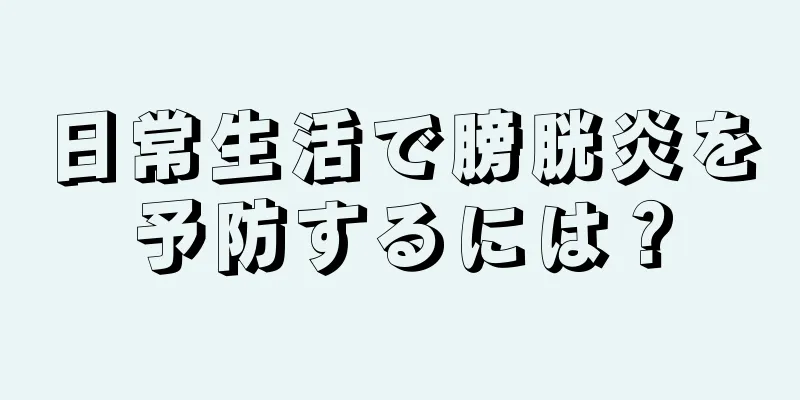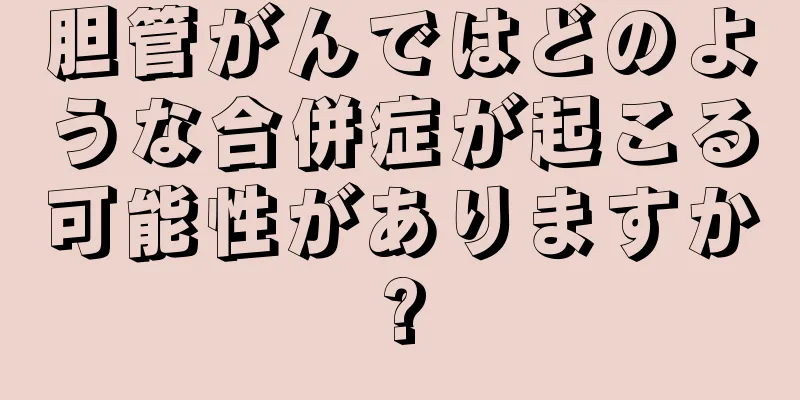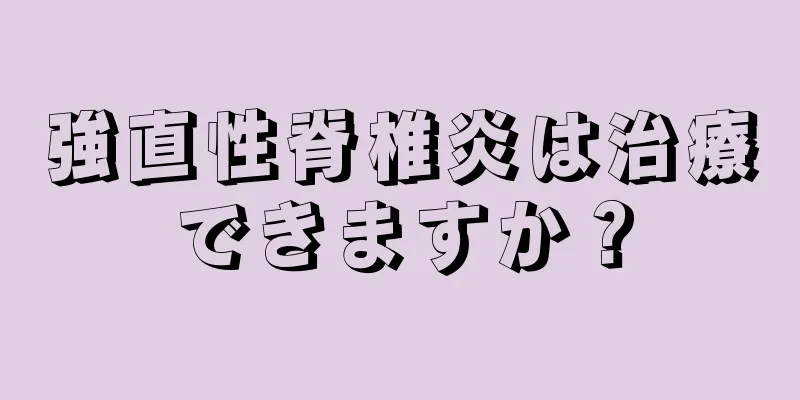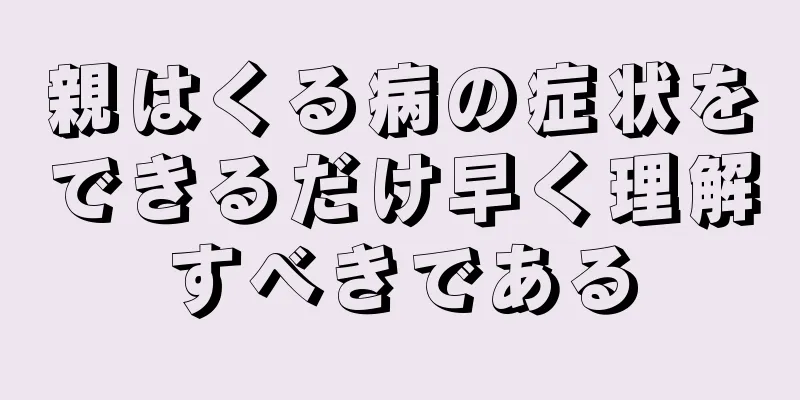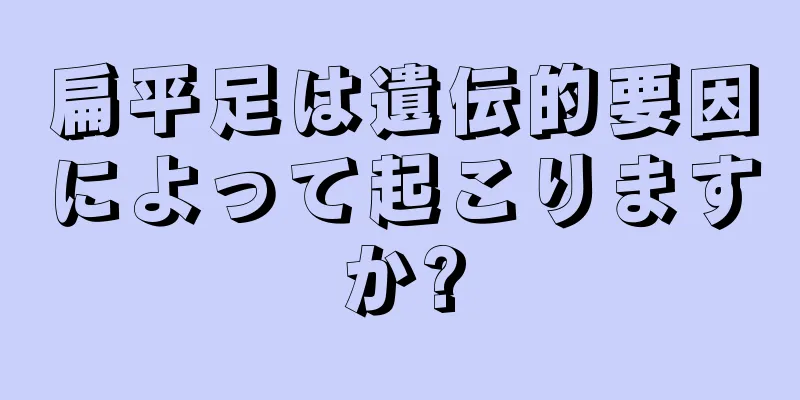強壮剤よりも小豆を食べた方が良い
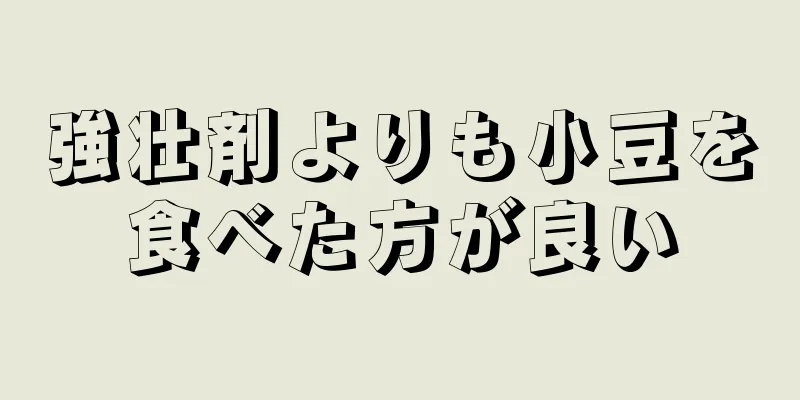
|
小豆は、小豆、赤小豆、紅豆とも呼ばれます。小豆はデンプン質が豊富なので、「米豆」とも呼ばれます。 「体液を調整し、排尿を促進し、膨満感を和らげ、腫れを取り除き、嘔吐を止める」という機能があり、李時珍によって「スプーンの谷」と呼ばれました。 小豆の栄養情報 小豆にはサポニン、食物繊維、葉酸などの成分が多く含まれています。 小豆の薬効 (1)小豆に含まれるサポニンは腸を刺激する働きがある。そのため、利尿作用に優れ、アルコールの排出や解毒に効果があり、心臓病、腎臓病、浮腫の患者にも有益です。 (2)小豆に含まれる食物繊維は、腸を潤して排便を促進し、血圧を下げ、血中脂質を下げ、血糖値を調節し、解毒して癌と闘い、結石を予防し、ボディービルと減量を促進する効果があります。 (3)小豆には葉酸が含まれています。小豆を多く食べると、産後女性や授乳中の母親の母乳の分泌を促進するのに役立ちます。 小豆を食べるときは、小豆の役割をよりよく果たすために、組み合わせに注意する必要があります。 1. 赤いナツメと組み合わせる。ナツメには鉄分が豊富に含まれており、小豆にも鉄分が豊富に含まれています。この2つを組み合わせることで鉄分補給が可能になり、血液補給にも効果的です。 2. ハトムギと組み合わせる。ハトムギと小豆の組み合わせは、便秘や排尿の緩和、毒素の排除、体内の浮腫の軽減に役立ちます。 3. 冬瓜と合わせる。小豆と冬瓜を一緒に食べると、体内の熱を減らして熱を和らげ、五臓六腑を養い、胃と脾臓を養い、肌に潤いを与え、肌に水分を補給して肌を健康に保つことができます。 小豆の選び方 小豆を食べる前には、必ず慎重に選んでください。品質の良い小豆を選ぶように注意し、腐った豆や悪い豆は買わないようにしてください。腐った小豆を食べると、下痢を起こしやすくなります。 1.表面を見てください。高品質の小豆の表面は赤みがかっており、粒が締まって充実しており、粒の大きさが非常に均一です。 2. 小豆の匂いを嗅いでみてください。良質の小豆には豆の匂いがあります。臭くて酸っぱい匂いがする小豆は腐った小豆です。 |
<<: ライチを食べた後に怒らないようにするにはどうすればいいですか?
推薦する
ファロー四徴症の重症度と
今では、ファロー四徴症が非常に深刻な病気であることは多くの人が知っています。この病気は積極的に治療す...
尿道炎の有害性の概要
尿道炎という病気について聞いたことがある人は多いかもしれませんが、この病気を本当に理解している人は多...
側方排卵障害の概要
婦人科疾患は女性の友人によく見られますが、知らない婦人科疾患もたくさんあります。今日お話しする排卵障...
小児くる病の臨床病期と症状
くる病の子供は、睡眠中に驚いたり、ちょっとした刺激で目が覚めたり、酸っぱくて悪臭を放ちながら大量に汗...
菊の品種によって効果は異なる
菊の役割は、観賞だけにとどまらず、食用として利用される方も多くなってきました。例えば、菊茶はよく飲ま...
五十肩にはどんな運動が効果的ですか?
大都市に住んでいるなら、生き残るために戦わなければなりません。さらに、今はコンピュータが普及した時代...
皮膚筋炎の食事療法には以下のものがある。
皮膚筋炎の食事療法には以下のものがある。皮膚筋炎は、後期に重篤な病気に発展することが多い病気です。そ...
直腸がんの手術後の放射線治療の副作用は何ですか?
直腸がんの手術後の放射線治療の副作用は何ですか?直腸がんの術後放射線療法の副作用には、一般的に皮膚損...
金や銀の宝飾品には放射線が含まれています。長期間装着するとガンの原因になりますか?注意:これらの5種類のジュエリーは体に害を及ぼす可能性があるため、できるだけ着用しないでください。
「先生、最近、金や銀のジュエリーには放射線があり、長期間身に着けているとガンの原因になるという話を聞...
胸膜炎患者は無酸素運動を行うことができますか?無酸素運動の最大の特徴は何ですか?
胸膜炎患者は無酸素運動を行うことができますか?運動は体力向上に良いです。激しい運動は無酸素運動ですが...
体のほくろは本当に安全ですか?小さな「ほくろ」が癌だったことが判明!
劉おじさんは63歳で、退職後は公園を散歩するのが習慣になっています。彼は長年、体にほくろがあったが、...
鼻咽頭がんの末期にひどい咳が出た場合の対処法
鼻咽頭がんの末期にひどい咳が出た場合はどうすればいいですか? 1. 鼻咽頭がんの後期段階では、患者は...
小葉性乳房肥大とはどういう意味ですか?
乳房肥大は非常に一般的であり、ほぼすべての女性に発生します。主な臨床症状は乳房の痛みであり、月経前に...
膀胱がんの症状は何ですか?
膀胱がんは日常生活において比較的よく見られる病気であり、多くの友人がこの病気に苦しんでいます。膀胱が...
長期にわたる朝食抜きは胆嚢ポリープの一般的な原因である
胆嚢ポリープの原因を理解することで、適切なタイミングで予防措置を講じることができます。 1. 朝食を...