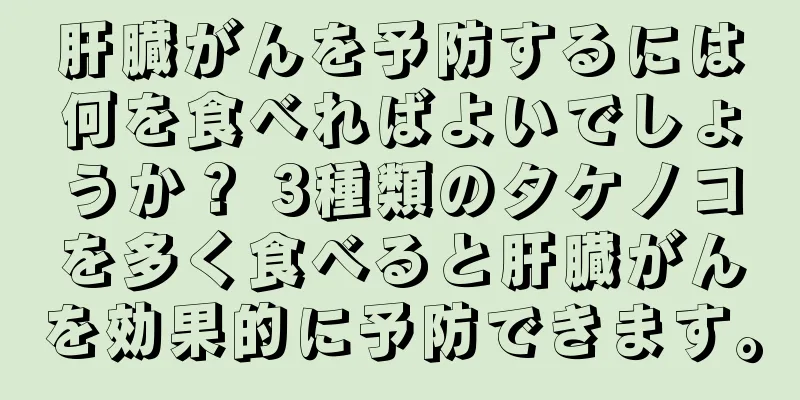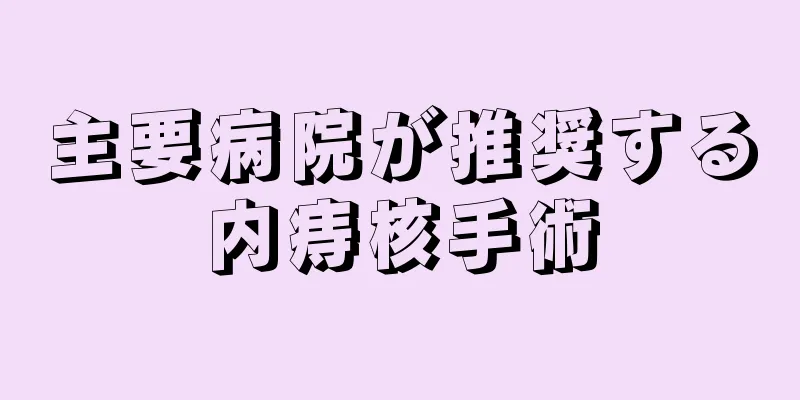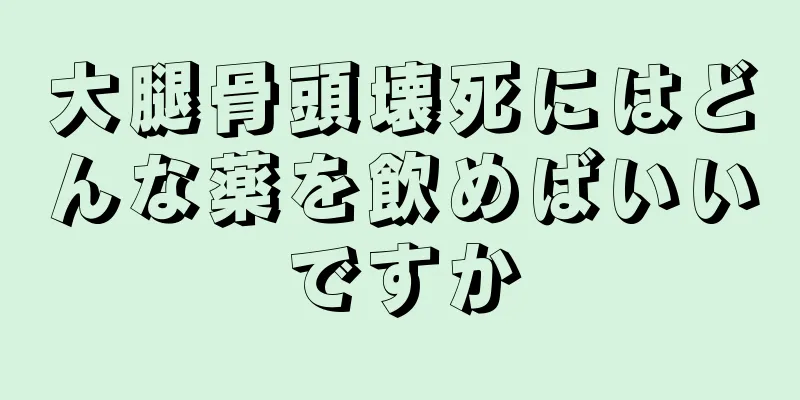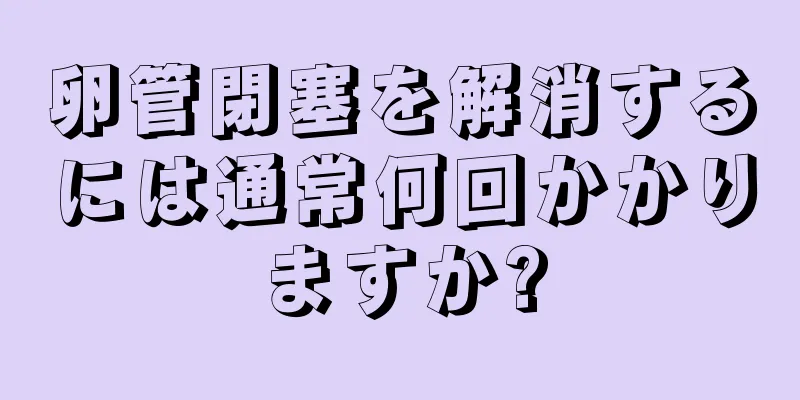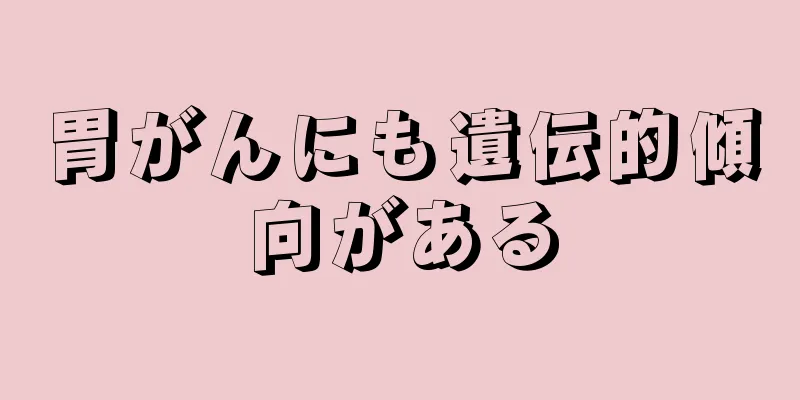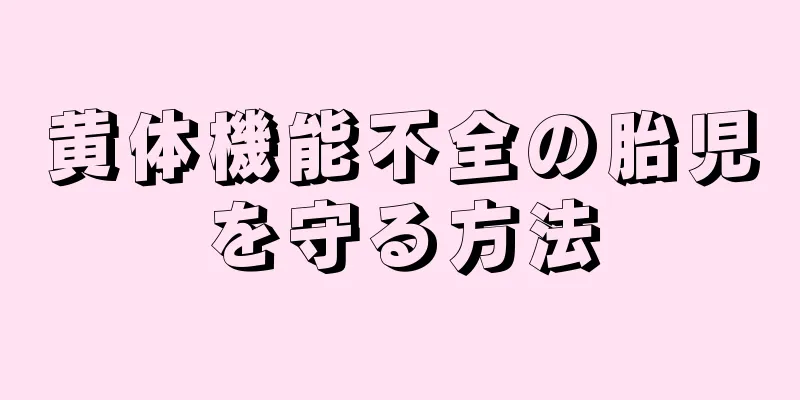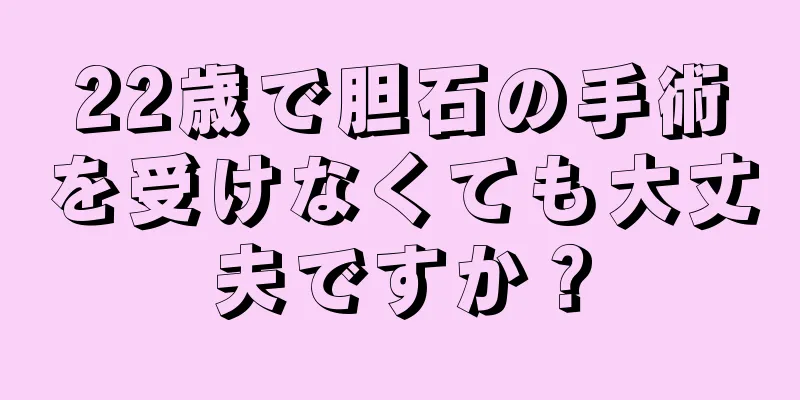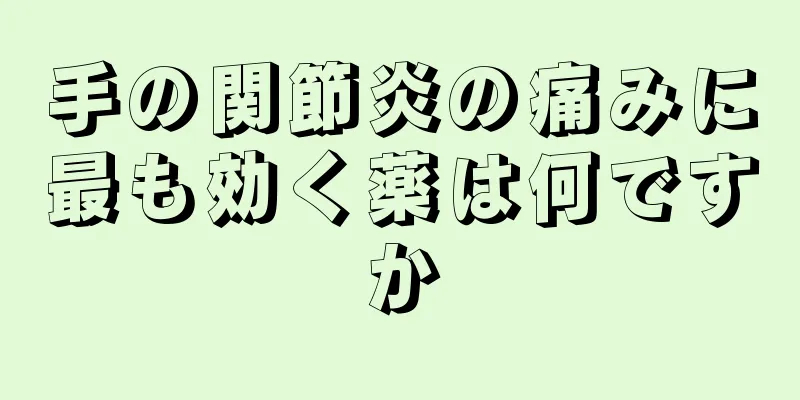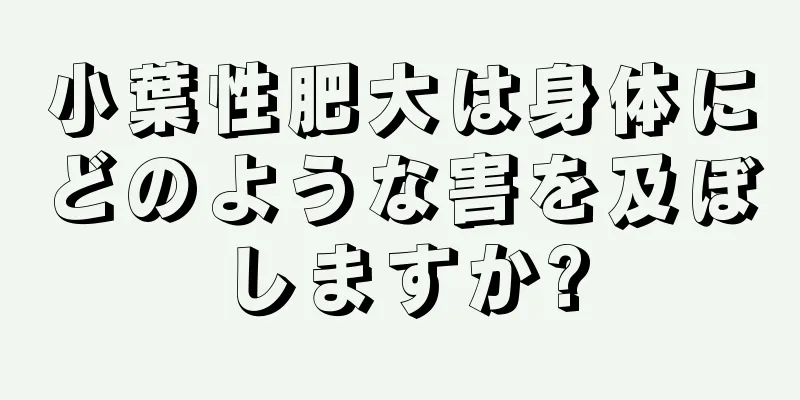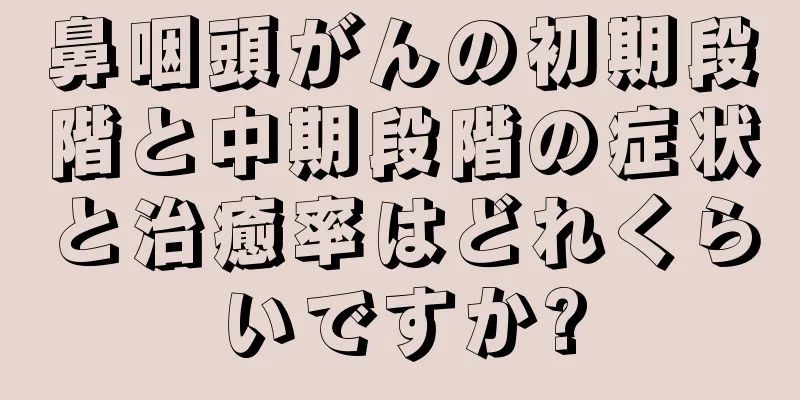骨粗鬆症治療薬は個性を重視
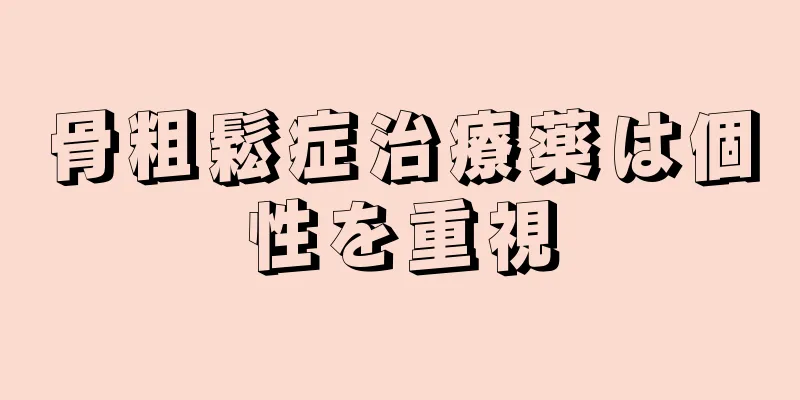
|
ご存知のとおり、骨粗鬆症は一般的かつ頻繁に発生する病気となっており、世界中で深刻化しています。しかし、一般の人々が骨粗鬆症について認識や関心を持っていないため、ほとんどの人は自分で治療薬を購入しています。不規則な自己投薬により、ほとんどの骨粗鬆症患者の治療効果は不十分です。骨粗しょう症による腰痛や骨折は高齢者の健康にとって深刻な脅威となっています。 骨粗鬆症治療薬による治療は、主に骨吸収の抑制と骨形成の促進が中心となります。臨床的に薬剤を選択する際には、患者の個々の状況に基づいて合理的に薬剤を選択し、個別化治療の原則を実施する必要があります。骨粗鬆症の薬物治療を選択する際には、次の 2 つの側面を考慮する必要があります。まず、治療対象となる患者にその薬が適しているかどうかを検討し、薬の適応症、副作用、禁忌など多くの側面を考慮する必要があります。次に、患者の年齢、性別、女性の場合は閉経時期、骨粗鬆症の程度、基礎疾患や合併症の有無など、患者の視点から検討します。 どのような病気の薬にも従うべき一定のルールがあり、骨粗鬆症の薬物治療にも臨床診断と治療のガイドラインがあります。これらのガイドラインに基づいて、基本的な対策や薬物治療など、治療薬の予備的な選択を行うことができます。基本的な対策としては、食生活の強化、運動の重視、悪い生活習慣の回避、転倒の予防などが挙げられます。治療薬としては、カルシウム剤、ビタミンD、その他の骨粗鬆症治療薬などがあります。これらをいかに合理的に組み合わせてより良い治療効果を達成するかが臨床治療の技術です。 カルシウムとビタミンDは基本的な薬です カルシウムの摂取量を適切に増やすと、骨の損失を遅らせ、骨の石灰化を改善できます。中国栄養学会は、成人が1日あたり800 mgのカルシウムを摂取することを推奨しています。これは、理想的な骨のピークに達し、骨の健康を維持するのに適切な量です。食事中のカルシウムの供給が不十分な場合は、カルシウムサプリメントを使用することができます。閉経後女性および高齢者の1日のカルシウムの推奨摂取量は1,000 mgです。しかし、私の国では高齢者が食事から摂取するカルシウムの平均1日摂取量はわずか400 mg程度です。したがって、牛乳2袋に含まれるカルシウムの量に相当する500~600 mgを補給する必要があります。 ビタミン D 欠乏症は二次性副甲状腺機能亢進症を引き起こし、骨吸収を増加させ、骨粗鬆症を引き起こしたり悪化させたりします。ビタミン D を適切に補給すると、胃腸管でのカルシウムの吸収に役立ちます。さらに、ビタミンDは高齢者の筋力とバランスを高め、転倒や骨折のリスクを軽減します。成人は毎日200単位以上のビタミンDを摂取する必要があります。若い人は日光浴や運動をすることが多いので、必ずしもサプリメントを摂る必要はありません。高齢者は日光不足や摂取・吸収障害などによりビタミンD欠乏症の症状が出ることが多いため、1日の摂取推奨量は400~800単位です。使用中は血清カルシウムと尿中カルシウムを定期的にモニタリングし、必要に応じて投与量を調整する必要があります。 患者がすでに骨粗鬆症を患っている場合、または骨粗鬆症の危険因子を伴う骨量減少症を患っている場合、あるいはすでに脆性骨折を患っている場合、カルシウムとビタミン D のみを補給するだけでは明らかに不十分です。骨吸収抑制薬や骨形成促進薬などの骨粗鬆症治療薬の服用を開始する必要があります。 ビスホスホネートは破骨細胞の活動を効果的に阻害し、骨の代謝回転を低下させます。研究により、アレンドロネートは腰椎と股関節の骨密度を大幅に高め、これらの部位の骨折リスクを大幅に軽減できることがわかっています。ごく少数の患者が、薬を服用した後に薬物逆流や食道潰瘍を経験します。したがって、薬をできるだけ早く胃に届け、食道への刺激を減らすために、朝の空腹時に200mlの水と一緒に薬を服用する必要があります。薬の吸収に影響を与えないように、薬を服用してから 30 分以内に食事をしないでください。食道の有害事象の増加を避けるため、30 分以内に横にならないでください。食道炎、活動性潰瘍のある患者、または長期間寝たきりの患者には注意して使用する必要があります。腎機能が低下している患者には禁忌です。 カルシトニンは破骨細胞の生物学的活動を阻害し、破骨細胞の数を減らし、骨粗鬆症患者の椎体骨折の発生率を低下させます。このタイプの薬剤のもう一つの優れた特徴は、骨の痛みを大幅に軽減し、骨粗鬆症による骨折や骨の変形によって引き起こされる慢性的な痛みに大きな効果があることです。したがって、痛みの症状がある骨粗鬆症患者に適しています。点鼻薬と注射薬の2種類があります。使用に際して明らかな禁忌はありませんが、まれにアレルギー反応が起こる場合があります。 エストロゲンは女性患者にのみ適しており、骨代謝を抑制し、骨量減少を防ぐことができます。臨床研究では、エストロゲンが骨粗鬆症患者の骨折リスクを軽減できることが十分に実証されています。更年期障害のある女性患者に特に適しています。エストロゲン依存性腫瘍、血栓性疾患、原因不明の膣出血、活動性肝疾患、結合組織疾患の患者は、この薬を使用することは禁止されています。子宮筋腫や子宮内膜症などのエストロゲン依存性疾患の患者には注意して使用する必要があります。 主な骨形成薬は副甲状腺ホルモンであり、高齢の重度の骨粗鬆症患者に使用されます。この薬は少量で使用すると骨形成を促進し、骨密度を効果的に高め、骨折のリスクを軽減します。しかし、大量に摂取すると骨に悪影響を与える可能性があります。したがって、投与量は多すぎてはならず、治療期間も長すぎてはならず、通常は 18 か月を超えてはなりません。重度の骨粗鬆症を治療する場合は、まず骨形成を促進する薬剤を使用し、次に骨吸収を抑制する薬剤を使用します。投薬中は高カルシウム血症の発症を防ぐため、血中カルシウム濃度のモニタリングに注意してください。しかし、市場に出回っているそのような薬は比較的少ないです。 フッ化ナトリウムも骨形成を促進する一定の効果がありますが、同時に骨の脆さを増し、骨折を起こしやすくなるため、臨床ではあまり使用されていません。 「一人でやる」ことには効果に限界がある 骨粗鬆症の治療において、1種類の薬剤だけを「単独で」使用した場合、その効果は非常に限られます。骨粗鬆症と効果的に闘うには、「多方面からの対策」を重視する必要があります。より良い抗骨粗鬆症効果を得るために、複数の薬剤を組み合わせて使用することもあります。たとえば、骨吸収を阻害する薬剤には、ビスホスホネート、エストロゲン、選択的エストロゲン受容体モジュレーター、カルシトニンなどがあります。一般的に使用されている薬剤は以下の 4 つです。骨形成を促進する副甲状腺ホルモンもあります。臨床における併用薬の使用は標準化されなければなりません。 一般的に使用されている臨床併用療法は次のとおりです。 カルシウム + ビタミン D: 老人性骨粗鬆症の治療の基本的な選択肢。この薬は安価で長期間服用しやすいです。 カルシウム + ビタミン D + ビスホスホネート、またはカルシウム + ビタミン D + カルシトニン: 骨粗鬆症の治療に最も一般的に使用される手段です。これら 3 つの薬剤を組み合わせることで、それぞれの利点を最大限に発揮し、互いの欠点を回避することができます。一定の経済力のある患者はこの組み合わせを選択できます。 エストロゲン + 「1」:つまり、エストロゲン + ビタミン D。エストロゲン + ビスフォスフォネートまたはエストロゲン + カルシトニン。閉経後の骨粗鬆症患者に適しています。研究によると、ビタミンD、ビスホスホネート、またはカルシトニンをエストロゲン療法と併用すると、エストロゲン単独療法よりも優れた臨床効果が得られ、エストロゲンの有効量と副作用の発生率が低下することが示されています。 |
推薦する
子宮内膜がんの出血は止まるのでしょうか?一般的にはそうではない
子宮内膜がんを患った後、不正子宮出血の症状が現れることがよくあります。治療しないと出血は自然に止まら...
大腸がんの化学療法にはどれくらいの費用がかかりますか?
大腸がんの化学療法にはどれくらいの費用がかかりますか?これは多くの患者が懸念している質問です。現在、...
心房中隔欠損症の見分け方
多くの患者は、体が強い信号を発したときにのみ治療のために病院に行きます。しかし、この時点では最適な治...
クラブアップルをもっと美味しくする方法
クラブアップルは、生のまままたは調理して食べるだけでなく、ワインや蜂蜜を作るのにも使用でき、ジャム、...
強直性脊椎炎の一般的な検査方法は何ですか?
腰椎の動きが制限され、硬直しているからといって、必ずしも強直性脊椎炎を患っているわけではありません。...
精巣がんの危険性は何ですか?
精巣がんはどんな害をもたらしますか?精巣がんを発症すると、男性の友人に与える被害は非常に大きくなりま...
乳房筋腫の原因は何ですか?
乳房疾患は現在、私たちの健康にますます影響を及ぼすようになっています。乳腺筋腫は、女性に特定の害を及...
トマトの色はその効能を決める
トマトはおいしい果物や野菜であるだけでなく、良い薬でもあります。現代の生物学および生理学の研究による...
肺がんを予防するには?
肺がんはがん疾患のひとつです。肺がんも私たちの日常生活でよく見られる病気です。では、肺がんに対しては...
高齢者が頻尿を緩和するために食べられる薬用食品は何ですか?
1.腎陽虚症状としては、頻尿、透明尿、頻尿だが尿が弱い、または残尿感があり、夜間に悪化するなどがある...
副乳をなくす方法
副乳房を除去する主な方法は手術です。少し怖いように聞こえますが、確かに現時点では最も効果的な方法です...
腰の筋肉の緊張によって引き起こされる腰痛の範囲は比較的広いです。
腰の筋肉の緊張によって引き起こされる腰痛の範囲は比較的広く、これらの特徴を通じて病状を発見することが...
糖尿病性膵臓がんの症状は何ですか?
糖尿病性膵臓がんの症状は何ですか?糖尿病患者は膵臓がんを発症するリスクが高く、膵臓がんは比較的隠れや...
肝臓がんに対する介入治療の利点は何ですか?
近年、肝臓がんは社会と人類の健康を脅かす主要な病気の一つとなり、人類に大きな苦痛と苦悩をもたらしてい...
パパイヤとクラブアップルは食べられますか?
パパイヤとクラブアップルは食べられますか?食べられますよ。 Malus 属は、高さ 7 メートルまで...