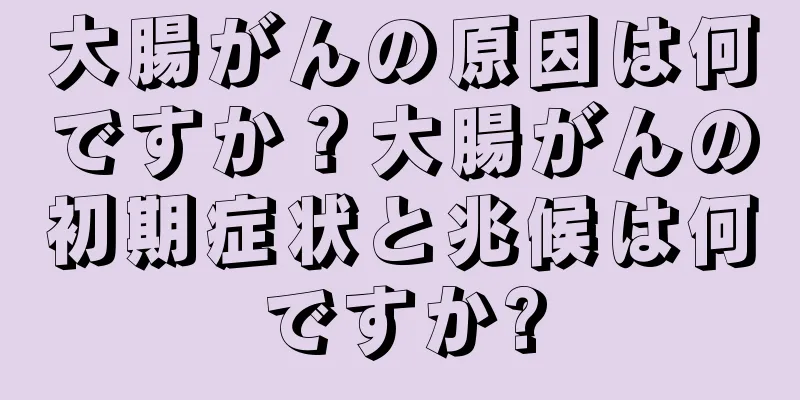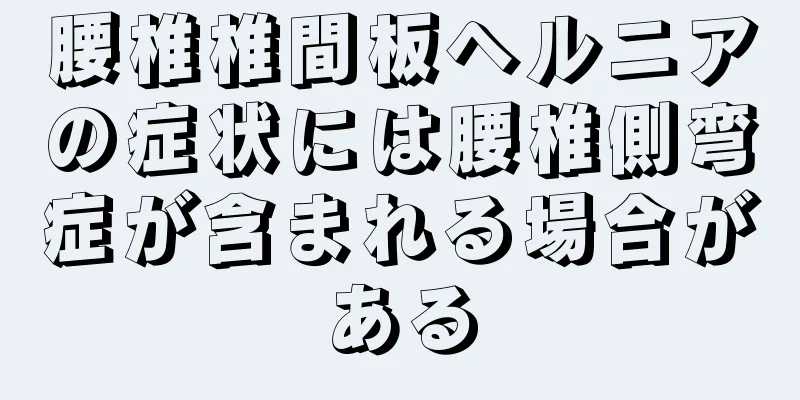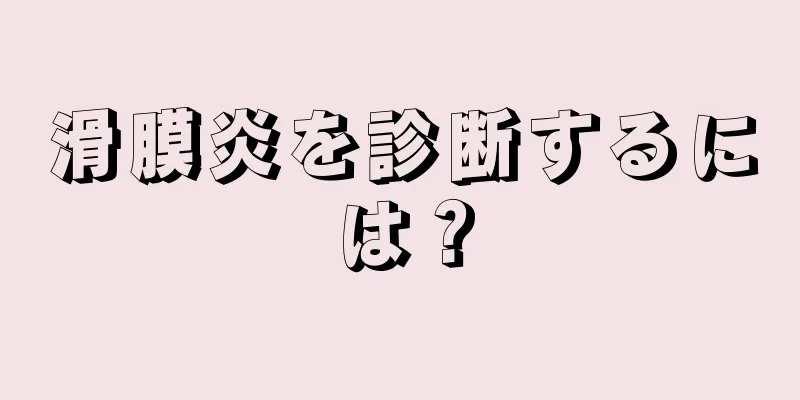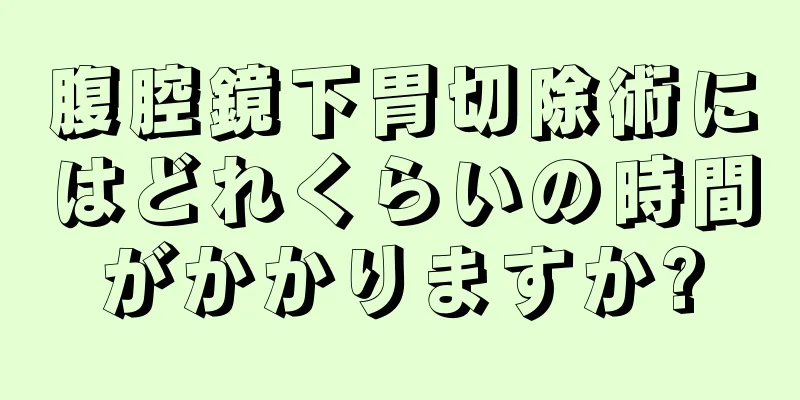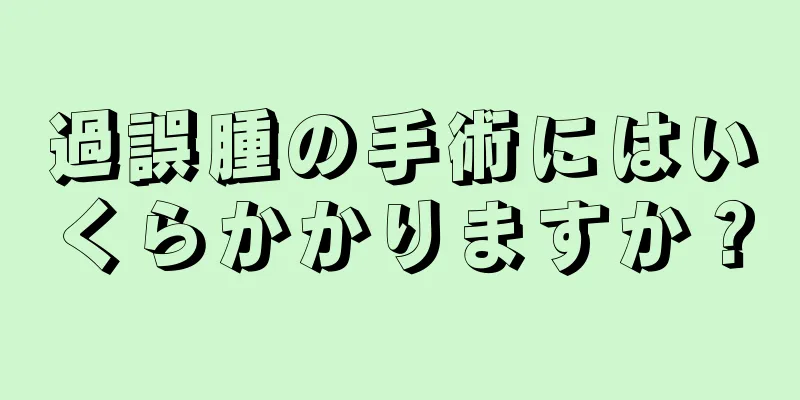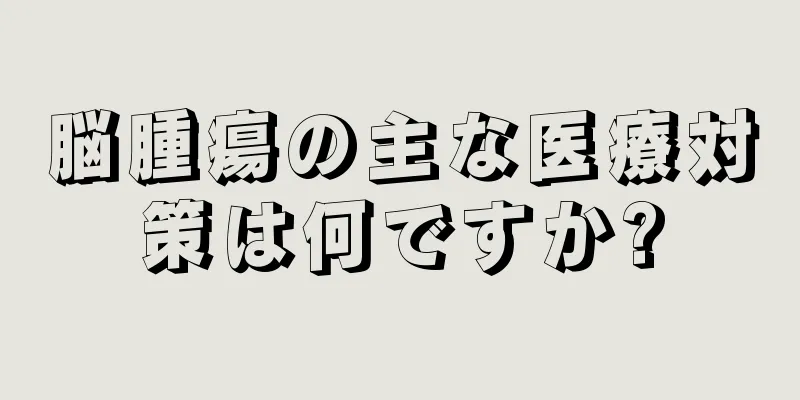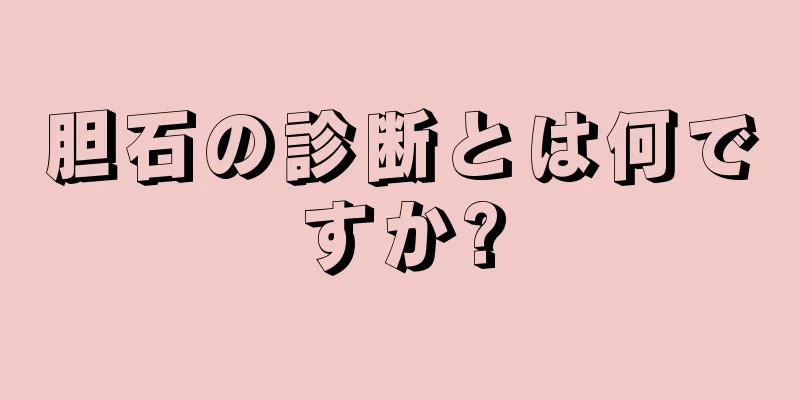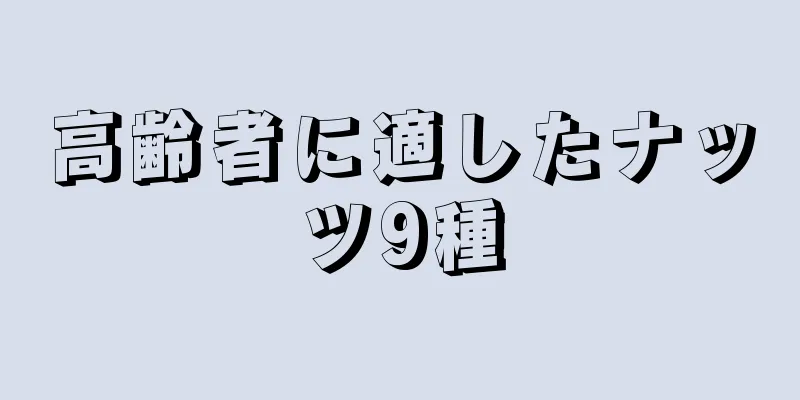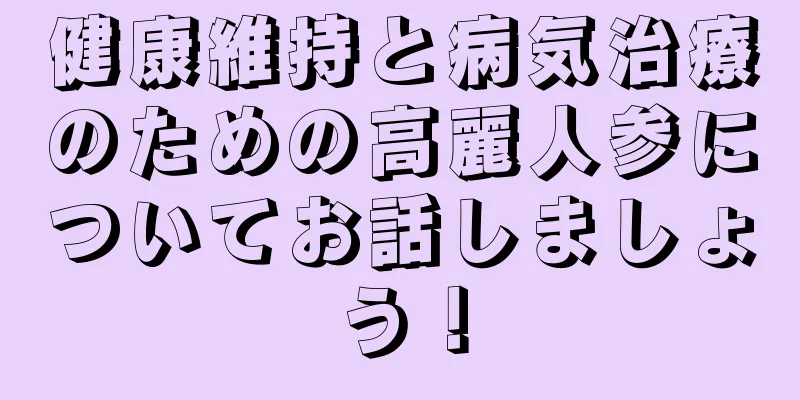腸閉塞は危険ですか?
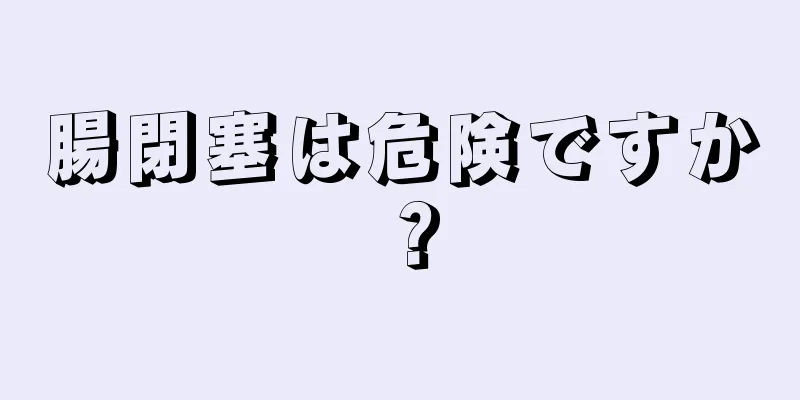
|
胃腸疾患にはさまざまな種類があります。一般的な腸炎に加えて、腸閉塞も比較的よく見られる病気です。腸閉塞になると、さまざまな症状が現れ、患者に大きな迷惑をかけることになります。では、腸閉塞の危険性とは何でしょうか?以下に紹介させていただきますので、ご参考になれば幸いです。 まず、腸閉塞になると、腹痛、吐き気・嘔吐、腹部膨満、肛門からのガスや排便の停止などの症状が現れます。 第二に、腸閉塞は水分、電解質、酸塩基の不均衡を引き起こす可能性があります。通常、唾液、胃液、胆汁、小腸液などの分泌量は1日あたり6000~8000mlです。通常の状況下では、これらの液体のほぼすべてが腸管によって吸収されます。腸閉塞の患者では、これらの体液は吸収されず、腸腔内に留まります。 第三に、腸閉塞は感染症や中毒を引き起こす可能性があります。腸閉塞により腸粘膜のバリア機能が損なわれ、細菌や毒素が腸壁を通過して腹腔内に侵入し、重度の腹膜炎を引き起こします。腸閉塞は腸壁の血液循環障害を引き起こし、続いて腸壊死や腸穿孔を引き起こす可能性があるため、腸閉塞は腸の絞扼壊死や腸穿孔を引き起こすこともあります。患者の中には、生命を脅かすショックや呼吸器系・循環器系の障害に苦しむ人もいます。 腸閉塞は、体内の老廃物の排出を妨げる病気です。病理学的要因または食事要因によって引き起こされる可能性があります。腸閉塞を引き起こす食品は以下の通りです。 1. 柿 柿は秋に出回り、お年寄りに愛されています。高齢者は全身のさまざまな臓器の退行性変化により腸の機能が低下し、秋柿は消化しにくくなります。高齢者が過剰に摂取すると、腸閉塞を起こす可能性があります。高齢者は腸の消化液の分泌が減少し、腸の蠕動運動が弱くなるため、習慣的な便秘につながることがよくあります。食べ物の残留物が便の中に蓄積すると、腸閉塞を引き起こすこともあります。 2. 魚卵 魚卵はタンパク質、カルシウム、リン、鉄、ビタミン、リボフラビンを多く含む栄養価の高い食品です。人間の脳と骨髄に良いサプリメントと成長剤です。発作性疝痛、吐き気、嘔吐、腹部膨満、便秘を治療します。しかし、魚卵にはコレステロールが多く含まれているため、高齢者はできるだけ食べないようにする必要があります。高齢者にとって、魚卵を多く食べるのは良くありません。腸閉塞、発作性疝痛、吐き気、嘔吐、腹部膨張、便秘、肝組織壊死または肝硬変などの疾患を引き起こす可能性があります。 3.シロキクラゲは栄養分が豊富で、腎臓を養い、肺を潤し、体液の生成を促進する効果があります。高齢者の間でもとても人気があります。しかし、臨床現場では、トレメラの不適切な摂取により高齢者が腸閉塞に悩まされることもよくあります。これは高齢者の消化機能が弱く、シロキクラゲが消化されにくいためです。一度に多量に摂取したり、連続して複数回摂取すると腸閉塞の原因になります。 |
<<: 腸閉塞を予防するためには生活のどのような点に注意すべきか
推薦する
グレープフルーツの食べ方!
グレープフルーツとユリのドリンク作り方:グレープフルーツ1個(重さ約500~1000グラム)の皮をむ...
肝血管腫の症状は何ですか?
私たちの周りにも肝血管腫の患者さんが何人かいます。病気にかかった後、初期症状は明らかではなく、病気が...
胆石治療の権威ある病院ランキング
胆石は、その出現が重大な危害を引き起こす可能性があるだけでなく、この病気の発生率が非常に高く、患者の...
皮膚腫瘍の初期症状を知る
皮膚腫瘍の初期症状を理解することが、早期発見と早期治療を実現するための最良かつ唯一の方法です。皮膚腫...
痛風性関節炎の診断基準は何ですか?
痛風性関節炎の診断基準は何ですか?痛風性関節炎は整形外科疾患の一種であることがわかっています。この病...
火傷から回復した後、皮膚が青白くなるのはなぜですか?
火傷ややけど後の傷の回復は誰もが心配する問題です。結局、もともと滑らかな肌に傷が残ることの方がみんな...
肝臓がんに対して身体はどのように反応するのでしょうか?肝臓がんの診断にはどのような検査が必要ですか?
肝臓がんなどの悪性腫瘍の場合、診断されるのは通常末期であることは誰もが知っています。では、原発性肝が...
血管炎の症状は何ですか?
私たちの友人のほとんどは血管炎という病気について知っていますが、それがどのような病気であるかを知らな...
下肢静脈血栓症と静脈瘤の違い
人生において、下肢静脈血栓症と静脈瘤はどちらも非常に一般的な病気です。これら 2 つの病気の症状には...
膀胱炎の症状と治療
膀胱炎は人生において比較的よくある病気であり、膀胱炎に罹ると患者に大きな苦痛をもたらします。では、膀...
関節炎の3つの症状
近年、関節炎の患者数が増加しています。関節炎の症状については、多くの人が大まかな理解を持っています。...
乳房筋腫の症状
私たちの周りの多くの女性の友人は、乳腺筋腫によって被害を受けています。この病気が発生すると、身体の健...
直腸がんの病理を理解する方法
近年、直腸がんは社会と人類の健康を脅かす主要な病気の一つとなり、人類に大きな苦痛と苦悩をもたらしてい...
初期段階の痔を治療するにはどうすればいいですか?初期の痔に最適な治療法
最近は、辛い食べ物を食べる人や、携帯電話を置いたままトイレに行く人が増えているため、痔に悩む人が増え...
人工股関節置換術後のリハビリテーション看護指導
大腿骨頭壊死の患者は、大腿骨頭がひどく潰れている場合、通常、股関節置換手術が必要になります。股関節置...