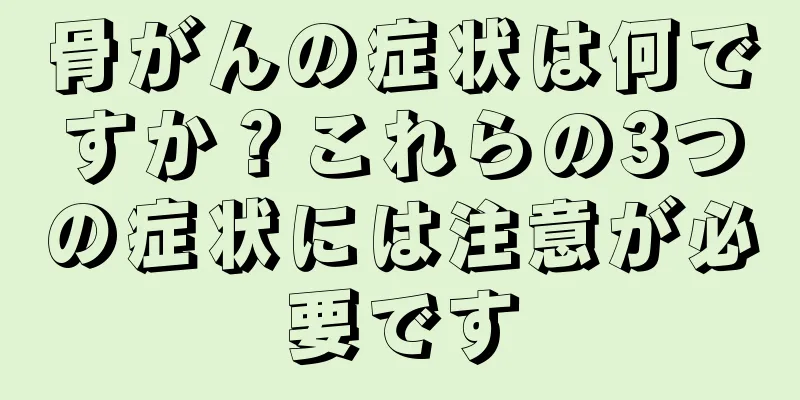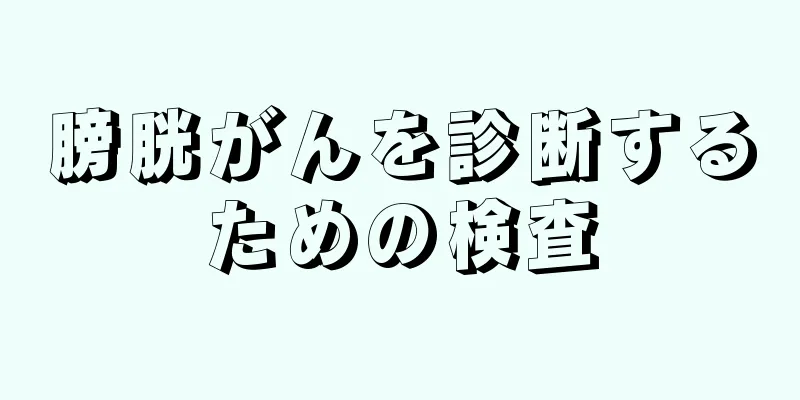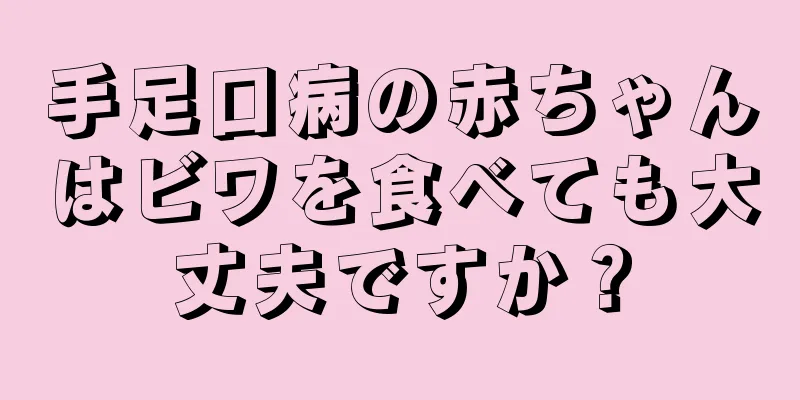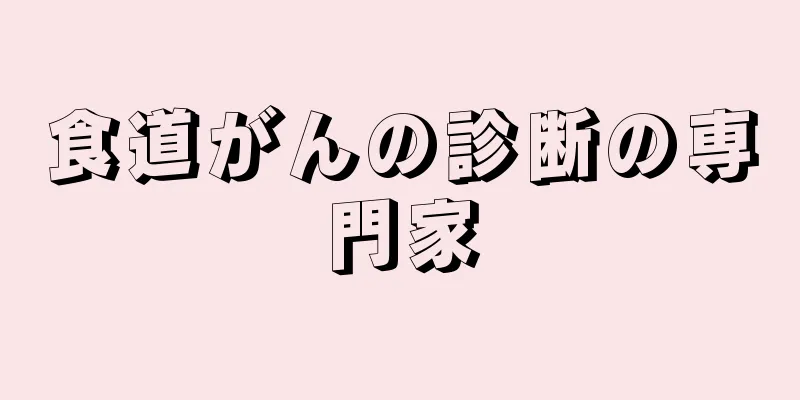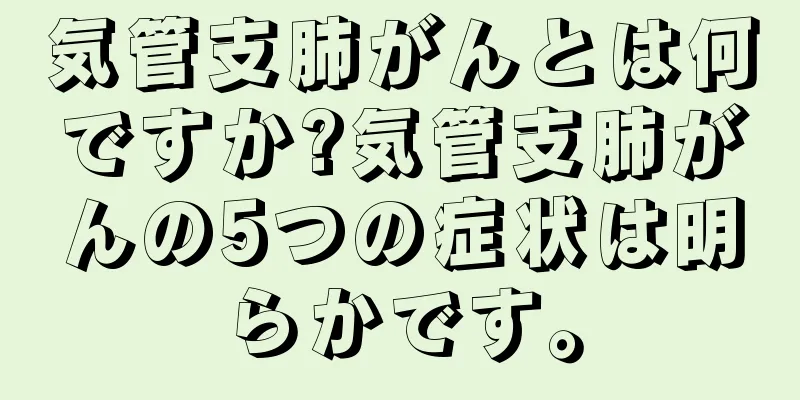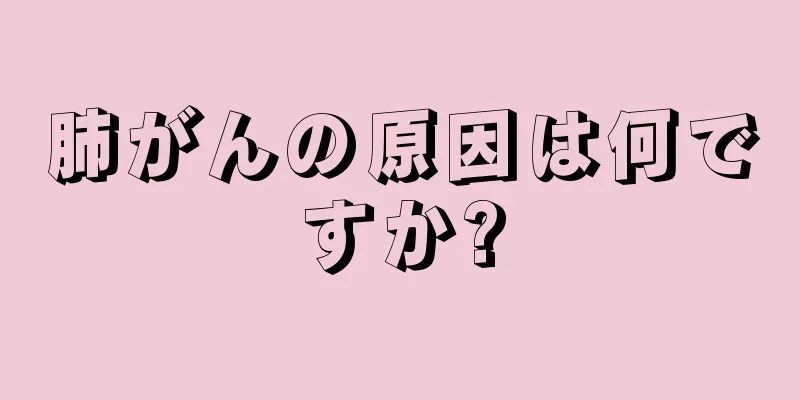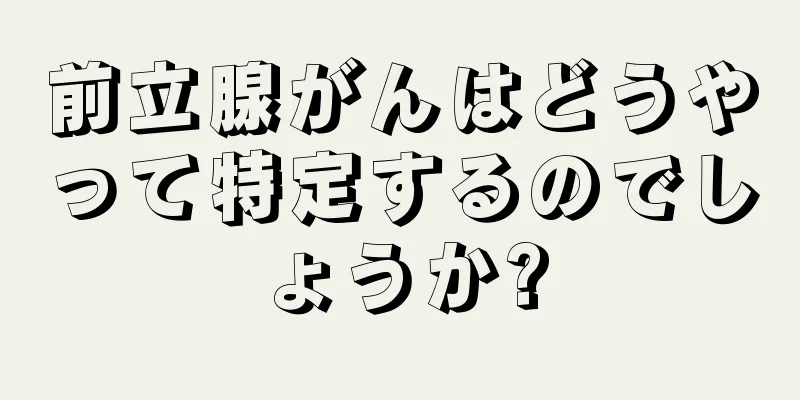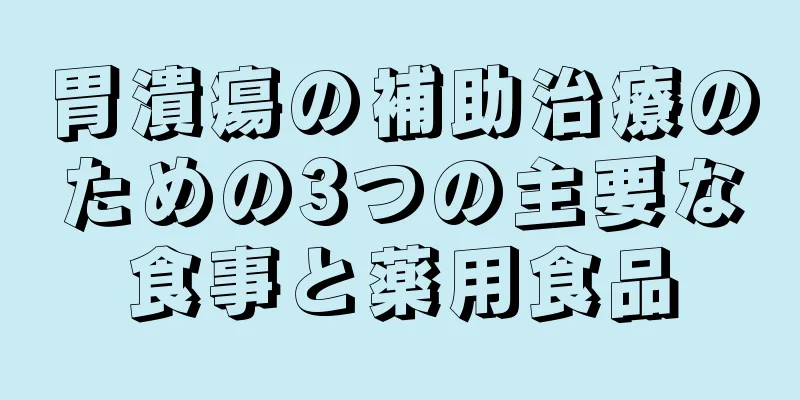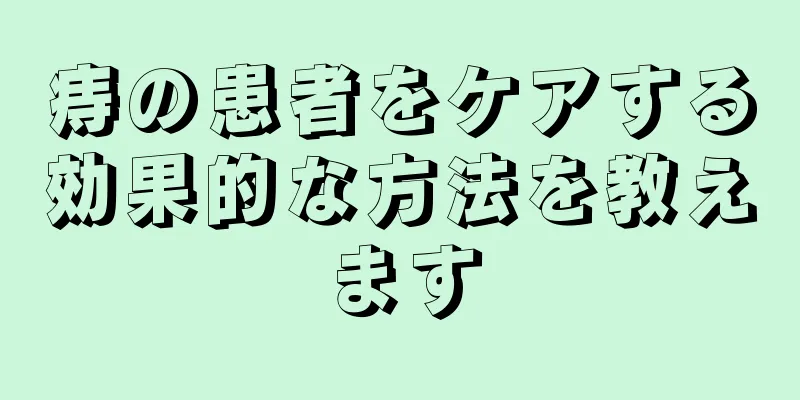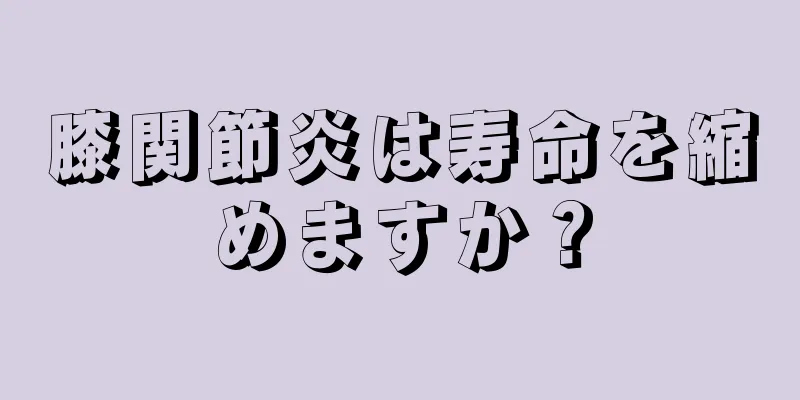胃がんは遺伝しますか?
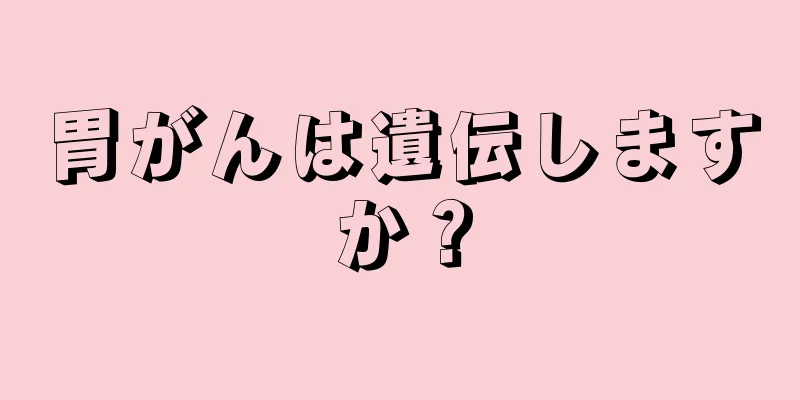
|
わが国では胃がんの発生率が非常に高く、家族内集積という現象がみられます。胃がんが遺伝性であるかどうかという疑問については、胃がんの発症における遺伝的要因の役割は大腸がんほど重要ではないものの、胃がんの家族歴は依然としてリスク要因である可能性があると一般的に考えられています。胃がんは家族内で集中的に発生する傾向があるため、家族内での発症率は一般人口の2~3倍高くなります。 遺伝的リスク: 胃がん患者は家族内で集積する傾向があることは明らかです。調査の結果、胃がん患者の第一度近親者(両親や兄弟)が胃がんを発症するリスクは一般人口の平均より3倍高いことが判明した。有名な例はナポレオンの家族です。彼の祖父、父、そして3人の姉妹は皆胃がんで亡くなった。本人を含め、家族7人が胃がんを患っていた。 予防と治療の原則:胃がんの危険因子には、運動不足、精神的鬱、喫煙、燻製食品の嗜好、塩分の多い食事の嗜好、肉の過剰摂取、ヘリコバクター・ピロリ感染、胃潰瘍などがあります。しかし、菌類や新鮮な果物を好むことは胃がんに対する防御因子です。胃がんの家族内集積はヘリコバクター・ピロリの同時感染と関係している可能性があることは注目に値します。胃がんの家族歴がある人は、病院に行ってこの細菌の感染を監視し、感染している場合は速やかに治療を受ける必要があります。カビの生えた食べ物は避けてください。私たちは日常生活の中で、カビが生えたり腐ったりした食べ物に遭遇することがよくあります。カビは汚染されたカビによって発生します。カビの中には、強力な発癌物質である毒素産生菌類もあります。同時に、一部の食品は毒素産生菌の作用により、大量の亜硝酸塩や第二級アミンを生成します。体内に入ると、特定の条件下でニトロソアミン化合物を合成し、がんを引き起こす可能性があります。 |
>>: 進行した乳がんの女性は、食事ができず腹部が膨張している場合、どれくらい生きられるのでしょうか?
推薦する
アレルギー性鼻炎患者に対する食事療法
食事療法は、伝統的な中国医学における病気の治療方法です。この方法は体を温め、強壮し、副作用がないため...
腎臓がんの術後検査項目は何ですか?
腎臓がんの患者は、断続的に痛みを伴う肉眼的血尿を経験することがよくあります。病気が進行するにつれて間...
甲状腺がんの白血球数が低い場合の対処法
甲状腺がん患者の白血球数の低下は、薬剤の副作用、甲状腺組織の損傷、または免疫抑制療法によって引き起こ...
前立腺がんを予防する方法は何ですか?
近年、前立腺腫瘍の発生率が増加しており、多くの医学者の注目を集めています。この病気の発生を減らすため...
胆管がんに効く漢方薬は何か
まずは、正規の病院に行って科学的な治療を受けましょう。手術後は医師の指示のもと、積極的にリハビリ訓練...
卵巣腫瘍の手術方法
卵巣腫瘍の手術はどのように行われますか?嚢胞が5cmより大きい場合は、チョコレート卵巣嚢胞であるため...
前立腺炎と膀胱炎の違いは何ですか?
前立腺炎と膀胱炎の違いは何ですか?多くの男性は、この病気についての十分な知識を持たず、この2つの病気...
痔は遺伝病ですか?
痔は人生においてよくある病気であり、どの年齢でも発症する可能性がありますが、発症率は年齢とともに徐々...
男性が前立腺がんを予防するのに良い6つの食品
前立腺がんは男性の健康を危険にさらす腫瘍性疾患ですが、適切な食品を摂取することで前立腺がんを予防でき...
肺微石症の予防策
この病気にかかっている人は日常生活でより注意を払う必要があります。全てが食べられるわけではありません...
膀胱がんの診断方法
膀胱がんは、泌尿器系で非常によく見られる悪性腫瘍疾患です。中高年の患者に多く見られ、女性よりも男性に...
脊椎変形患者の典型的な症状を簡単に説明する
脊椎変形は一般的な整形外科疾患です。一度発生すると、身体に大きな害を及ぼします。患者は脊椎変形の症状...
へそシールで痔を治療する
痔の治療にへそにシールを貼るというのは魔法のように聞こえるかもしれないが、実際には民間療法である。痔...
鼻咽頭癌に関連する要因は何ですか?
鼻咽頭癌は私の国ではよくある悪性腫瘍です。がんの中でも死亡率が高く、我が国の鼻咽頭がんの発生率は世界...
柿の食べ方4つ
甘柿の焼きブリュレ材料: シャキシャキした柿500g、生クリームと牛乳各300ml、白砂糖60g、卵...