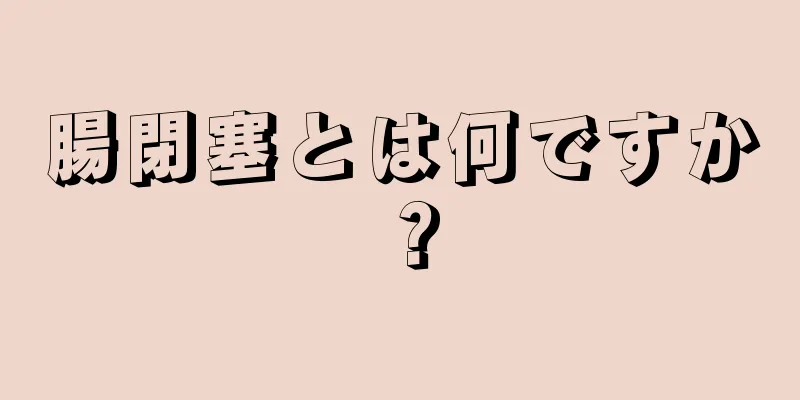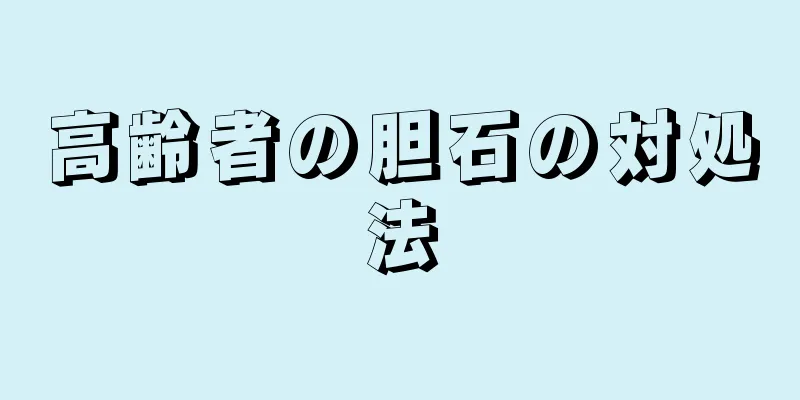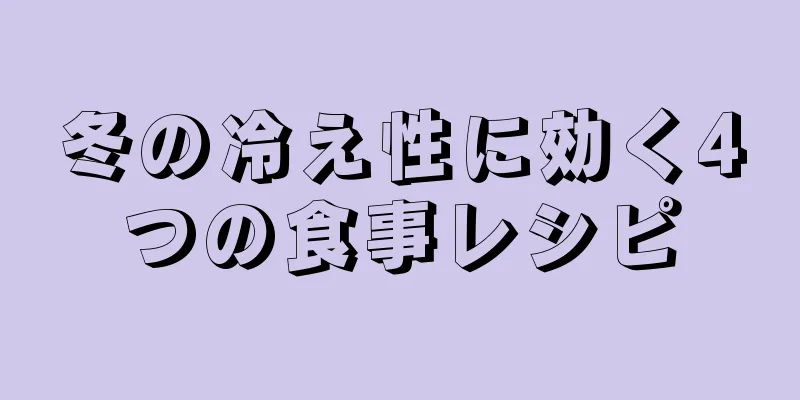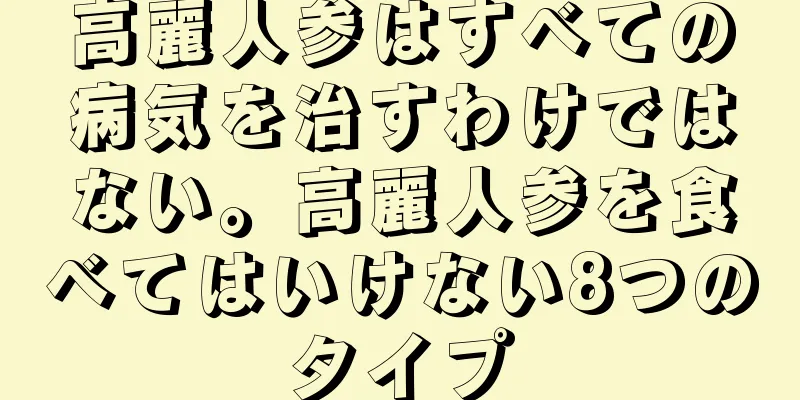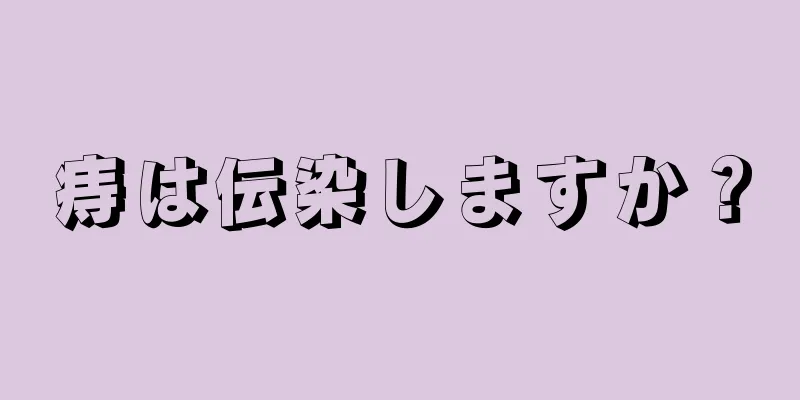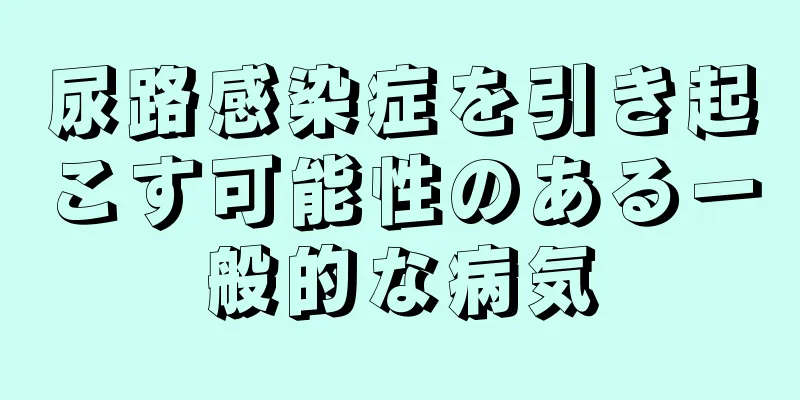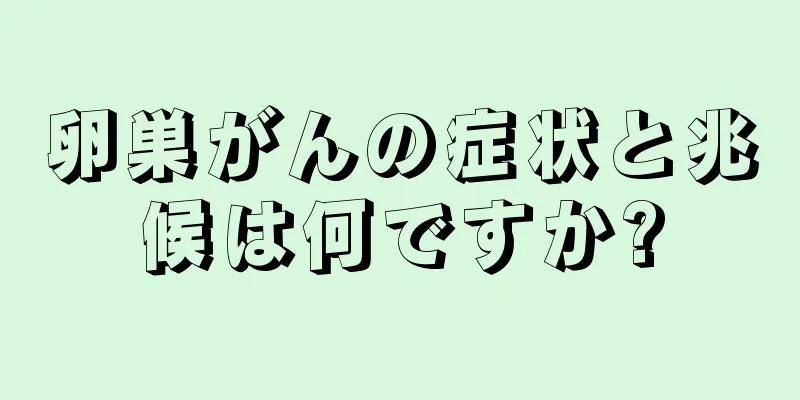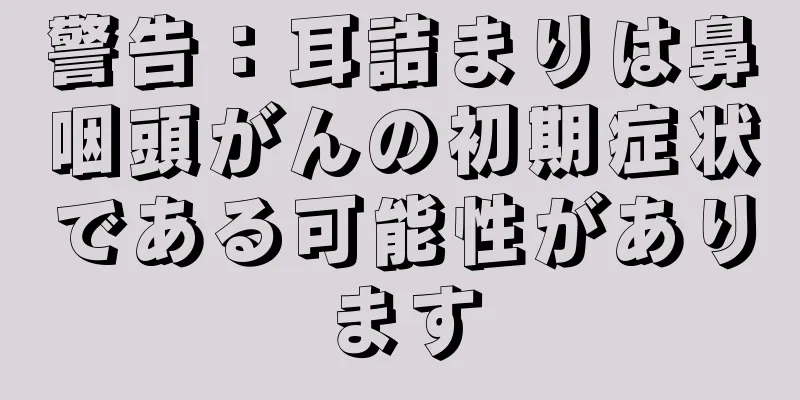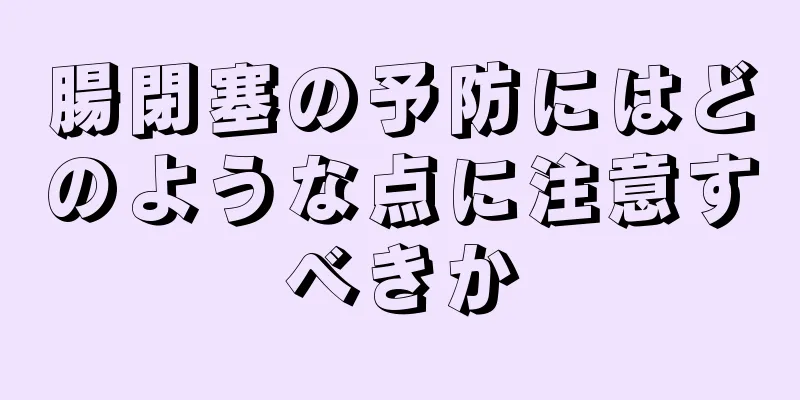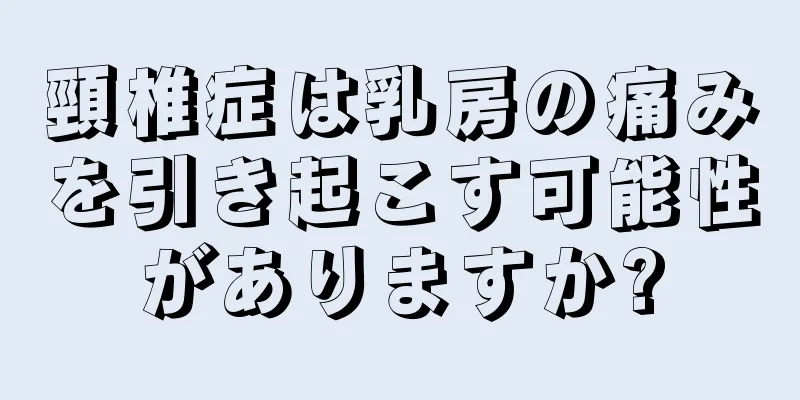頚椎症の予防:日常生活での注意点
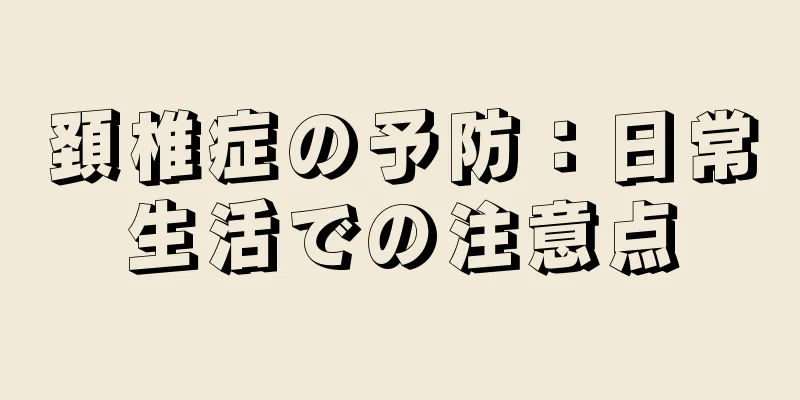
|
頸椎症は若者の間でも増加傾向にあります。 20代、30代の若者が頸椎症の主なターゲットになっています。十代の若者でも、かなりの数の人が頸椎症に悩まされています。これは若者の仕事の性質だけでなく、学習姿勢や学習の強度にも密接に関係しています。したがって、良好な仕事と生活習慣を身につけることは、頸椎の健康を維持し、頸椎症を予防するために特に重要です。 1. 座る時間を減らして、動く時間を増やす: 1 時間働いた後は、立ち上がって動き回ってください。コップ一杯の水を飲んだり、手足を伸ばしたりすることで、頸椎の緊張を和らげ、首の筋肉の強さを高めることができます。午前中ずっと座っていると、筋肉が疲労しやすくなり、頸椎がさらに疲労し、遅かれ早かれ頸椎症を発症します。 2. カルシウム補給:カルシウムは骨の強度を高め、首の骨を柔軟で強くします。医師の指導のもとでカルシウムのサプリメントを摂取し、同時に大豆製品、乳製品、魚介類などカルシウムを多く含む食品を多く食べるように注意しましょう。 3. 麻雀をあまりしない: 麻雀をするときは、勝つか負けるかにエネルギーが集中するため、首が長時間曲がった姿勢を無視してしまいます。時間が経つにつれて、首のこり、首の痛み、動きの制限を引き起こし、最終的には上肢の衰弱、手足の皮膚感覚の低下などにつながります。したがって、すぐに麻雀テーブルから離れてください。 4. 適切な枕を選ぶ: 枕の主な機能は、人体の正常な生理的曲線を維持し、睡眠中に頸椎の生理的曲線が変化しないようにすることです。したがって、枕の高さ、長さ、柔らかさ、硬さは、頸椎の健康維持に密接に関係しています。 5. ハイヒールを履かない: ハイヒールを履くと背が高く見え、魅力的に見えますが、頸椎への負担が大きくなります。女性がハイヒールを履くと、重心が前方に移動し、背骨の湾曲が増し、腰椎と頸椎にストレスが集中します。何年も経つと、最終的には頸椎症につながります。 |
推薦する
乳がんの初期症状と兆候
乳がんは、初期段階では以下のような症状や前兆が現れることがあります。乳がんの一般的な初期症状には、乳...
良性リンパ腫の症状は何ですか?
良性リンパ腫は、間質組織内の血流の停滞によって引き起こされる細胞腫脹の一種です。初期症状は明らかでは...
甲状腺がんはなぜ歯のしびれを引き起こすのでしょうか?
甲状腺がんは、甲状腺濾胞上皮または濾胞傍細胞から発生する悪性腫瘍です。歯のしびれは、甲状腺がんによる...
乳房嚢胞がある場合、純粋な牛乳やヨーグルトを飲んでも大丈夫ですか?
乳房嚢胞のある患者は通常、純粋な牛乳やヨーグルトを適度に飲むことができます。これら 2 つの乳製品は...
胚の発育が止まったらどうするか
胚不妊症とは、妊娠初期に何らかの理由で胚の発育が停止することを指します。 B超音波検査では、胚または...
心房中隔欠損症の治療はどこで受けられるか
心房中隔欠損症の治療にはどこに行くのが最適ですか?これは多くの患者とその家族にとって懸念事項です。間...
脳腫瘍を予防するにはこれらの食品を避けましょう
食事は私たちの生活においてとても重要です。どんな病気であっても、食生活には注意を払うべきです。病気は...
高齢者がオレンジを食べるとどんなメリットがあるのでしょうか?
脳卒中は、身体的および精神的健康の両方を危険にさらす病気です。では、高齢者にとってオレンジを食べると...
プーアル茶の役割!
プーアル茶の役割1. 脂肪を減らし、体重を減らし、血圧を下げ、動脈硬化を予防します。プーアル茶の臨床...
膀胱がんの末期に下痢をした場合、どれくらい生きられるのでしょうか?
膀胱がんの末期では下痢をしながらどれくらい生きられるのでしょうか?膀胱がんは遠隔転移やリンパ節転移が...
腰椎椎間板ヘルニアの症状は何ですか?
腰椎椎間板ヘルニアの症状は何ですか?腰椎椎間板ヘルニアの症状は、圧迫された神経を介した異常な信号伝達...
中期の鼻咽頭がんでも手術は可能ですか?
悪性腫瘍である鼻咽頭がんの初期症状はあまり明らかではありません。発見された時点では、癌の中期から後期...
良い生活習慣が直腸がん予防の鍵
わが国における直腸がんの罹患率は比較的高く、直腸がんに苦しむ人も多くいます。日常生活で積極的な予防策...
扁平足かどうか確認するには?
扁平足かどうか確認するには?扁平足は主に、足の形の異常、筋肉の萎縮、靭帯拘縮、または慢性的な緊張によ...
リュウガンを食べ過ぎるとどうなりますか?
リュウガンは美味しいですが、体内の熱を引き起こしやすいので、通常、1人あたり1日6両以上食べてはいけ...