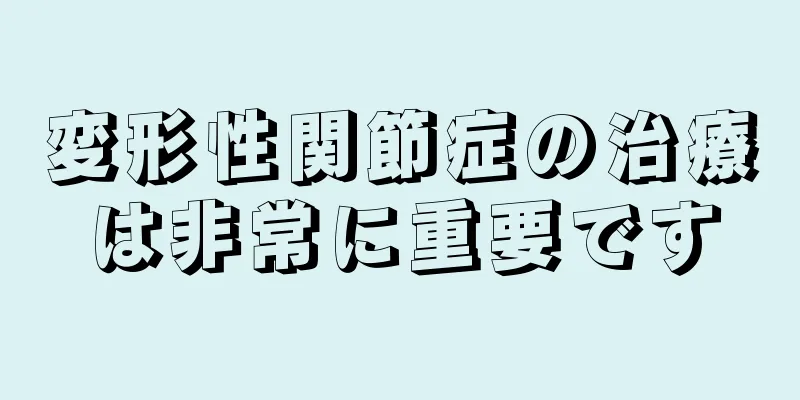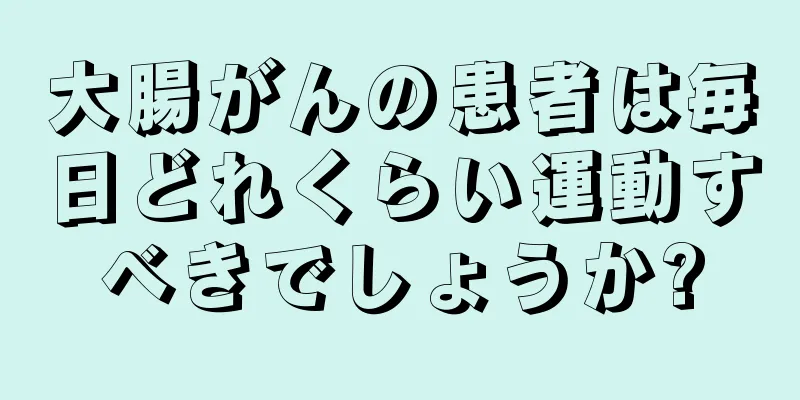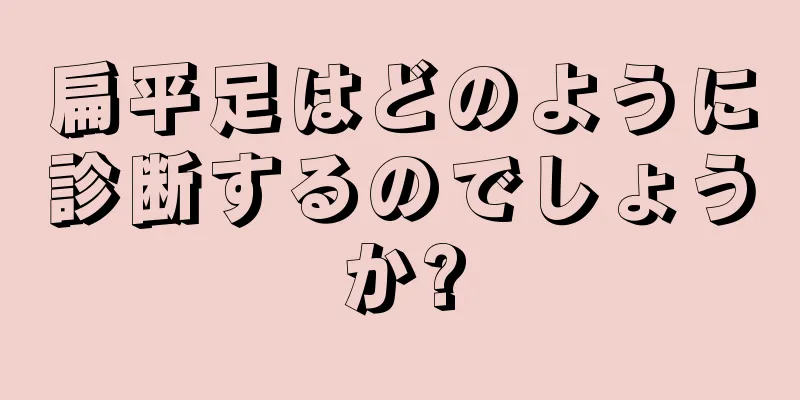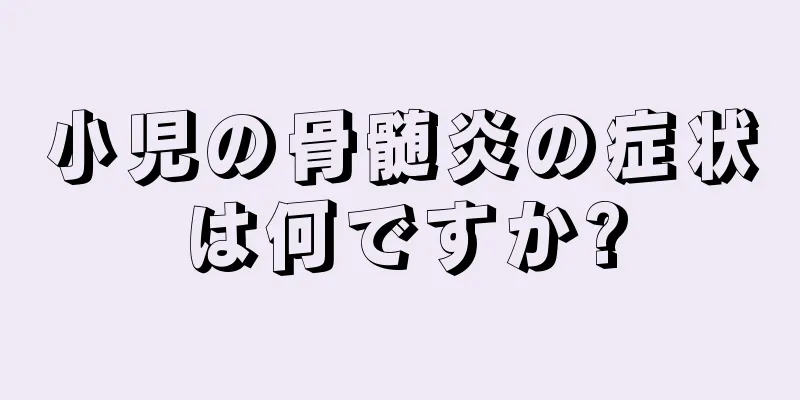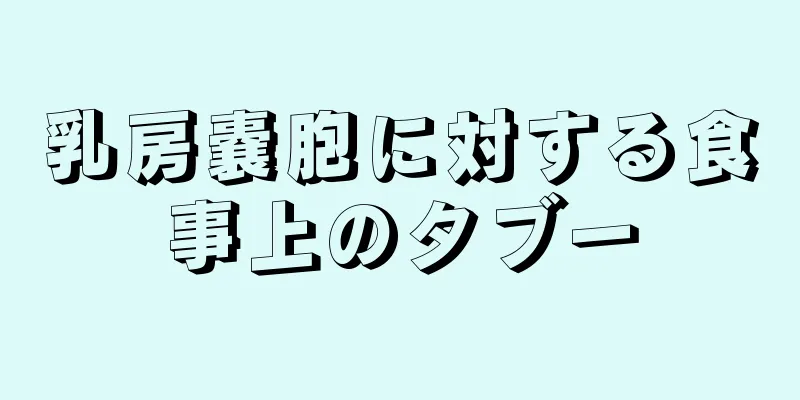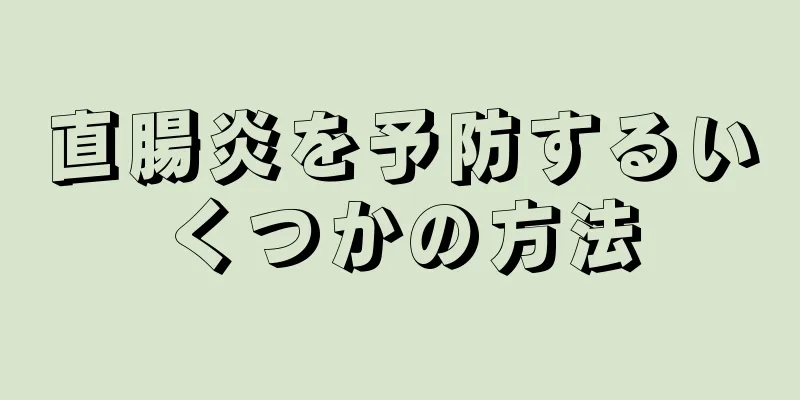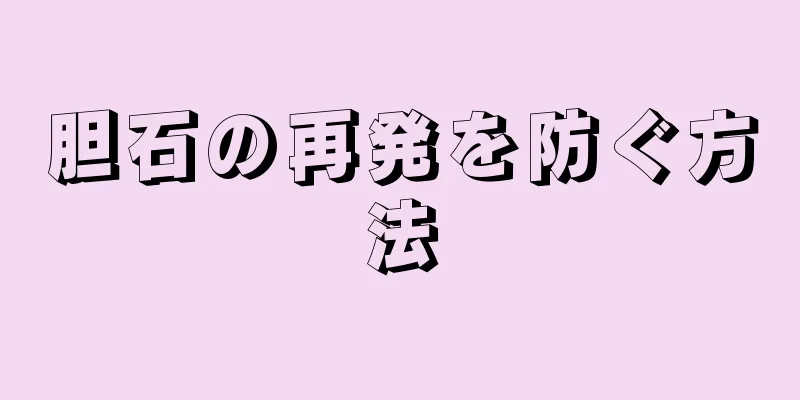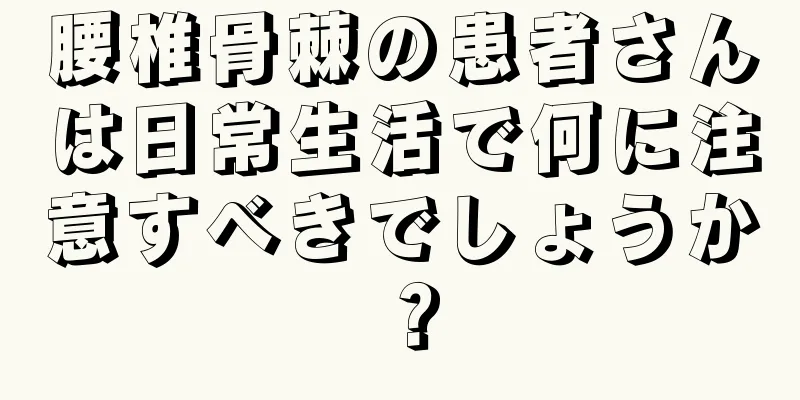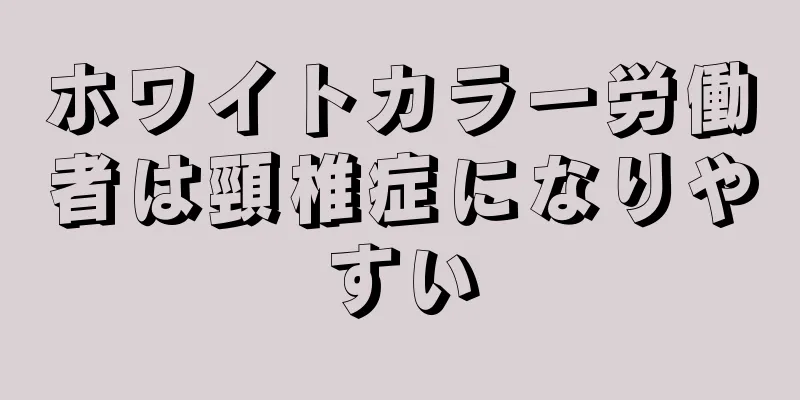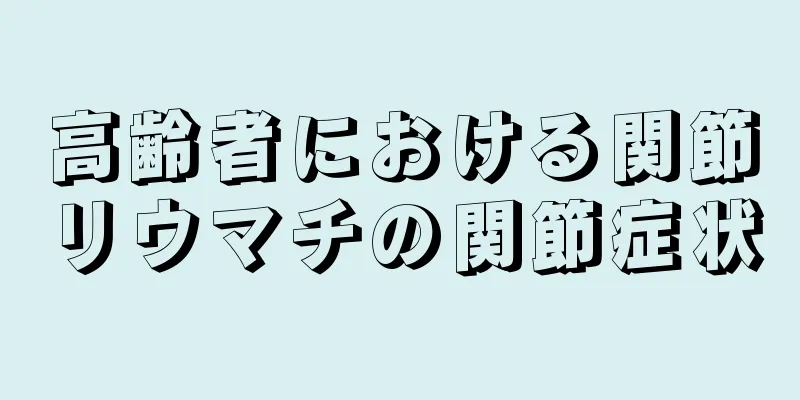くる病の臨床症状
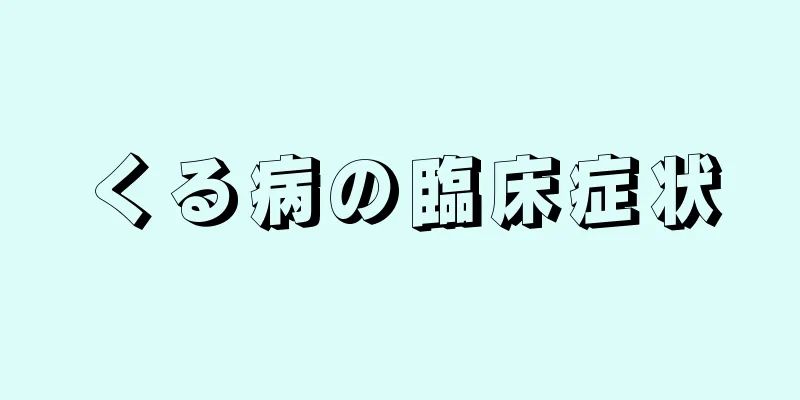
|
くる病は思春期によく起こることは誰もが知っています。この時点では、思春期の子どもはまだ完全には成長しておらず、抵抗力や免疫力も弱い状態です。カルシウム欠乏症がすぐに発見されないと、くる病が発生します。では、くる病の臨床症状とは何でしょうか?専門家の回答は以下をご覧ください。 乳児や幼児、特に 3 ~ 18 か月の小児によく見られます。主な症状は、最も成長の早い部分の骨の変化であり、筋肉の発達や神経の興奮性の変化に影響を及ぼす可能性があります。臨床症状は年齢によって異なります。この病気は臨床的に以下のように分類されます。 早い これは生後 6 か月未満の乳児、特に生後 3 か月未満の乳児に発生し、イライラ、落ち着きのなさ、発汗による頭皮の炎症や頭の震えなど、神経の興奮性が高まるのが特徴です。この期間中には通常骨病変はなく、骨のX線検査は正常であるか、石灰化帯がわずかにぼやけている場合があります。血清25-OH-D3が減少し、PTHが増加し、血中カルシウムが減少し、血中リンが減少し、アルカリホスファターゼは正常またはわずかに高くなります。 活動期 病気が悪化し続けると、PTH 機能亢進やカルシウムとリンの代謝異常などの典型的な骨の変化が現れます。生後 6 か月未満の乳児のくる病は、主に頭蓋骨の変化、大泉門の縁が柔らかくなること、頭蓋骨が薄くなること、軽く押すと「ピンポン玉」のような感触になることが特徴です。生後6か月を過ぎると、縫合部周辺にピンポン玉のような感触が残ることもありますが、前頭骨や頭頂骨の中央部分が徐々に厚くなることが多いです。生後7~8か月になると、頭の形が「四角い」形になり、頭囲が正常よりも大きくなります。骨端線端は骨様組織の蓄積により膨隆し、肋骨と肋軟骨の接合部には肋骨方向に沿って丸い突起が触れます。上から下にかけてビーズのような突起があり、第 7 肋骨から第 10 肋骨にかけて最も顕著に現れます。これをくる病ロザリオといいます。重症の場合、手首や足首に鈍い丸いリング状の突起が形成されることもあり、これをブレスレットと呼びます。 1 歳前後の子供では、胸骨と隣接する軟骨が前方に突出し、「鳩胸のような」変形を形成しているのが見られます。重度のくる病を患う小児では、胸郭の下端に水平方向のくぼみ、すなわち肋骨横隔膜溝またはハリソン溝が形成されます。 子供が座ったり立ったりするときに、靭帯が緩んで脊椎の変形を引き起こす可能性があります。骨軟化症や筋肉や関節の弛緩により、1歳を過ぎて立ったり歩いたりするときに下肢に体重がかかり始めると、大腿骨、脛骨、腓骨が曲がり、重度の外反膝「O」字型または外反膝「X」字型の下肢変形を形成することがあります。重度の低リン血症は筋肉の糖代謝障害を引き起こし、全身の筋肉の弛緩、筋緊張の低下、筋力の低下を引き起こす可能性があります。 この期間中、血清カルシウムがわずかに低下したことを除き、他の血液生化学指標の変化はより顕著です。 X 線では、長骨の石灰化帯が消失し、骨端線がブラシ状やカップ状になっていることがわかります。骨がまばらになり、皮質骨が薄くなる。骨幹部の湾曲や若木骨折が発生する可能性があり、骨折には臨床症状がない場合があります。 回復期間 上記のいずれかの段階で治療または日光曝露を行った後、臨床症状および徴候は徐々に緩和または消失します。血中のカルシウムとリンは徐々に正常に戻りますが、アルカリホスファターゼが正常値に戻るまでには1~2か月ほどかかります。治療開始から2~3週間後、骨のX線変化は改善し、不規則な石灰化線が現れました。その後、石灰化帯はより密で厚くなり、徐々に正常に戻りました。 後遺症 2歳以上の子供によく見られます。幼児期の重度のくる病により、臨床症状はなく程度の異なる骨変形が残存しており、血液生化学検査では正常であり、X線検査では骨端骨の病変が消失していることが示された。 上記の紹介を通じて、くる病の臨床症状がわかりました。日常生活では、そうなる前に予防策を講じ、子どもの身体の変化を注意深く観察し、定期的にカルシウムを補給する必要があります。これらは、症状を予防し、早期に検出するのに役立ちます。体調が悪くなったら、すぐに病院に行って診断を受ける必要があります。 |
推薦する
喉頭がんの初期症状は何ですか?
喉頭がんは喉に発生する悪性腫瘍を指します。初期段階では明らかな不快感は現れないかもしれませんが、喉の...
骨折が治癒した後の再発のリスクは何ですか?
骨折は一般的な整形外科疾患であり、人生において時々起こります。骨折は多くの人に害と迷惑をもたらしてい...
乳がん手術から1年後の食事のタブーは何ですか?
乳がんの手術から 1 年後の食事上のタブーとしては、高レベルのホルモンを含む食品の摂取を禁止すること...
日常生活におけるO脚の害の分析
日常生活において、O脚に悩まされている人は多く、心身の健康に深刻な影響を及ぼし、ひどい場合には劣等感...
貧血ダイエットレシピ
貧血ダイエットレシピマザーワートとナズナの炒め物作り方:新鮮なマザーワート3グラム、新鮮なナズナ30...
肘頭骨折にはどのような検査が必要ですか
肘頭骨折にはどのような検査が必要ですか?肘頭骨折は一般的な整形外科疾患ですが、より危険です。肘が損傷...
早期の急性鼻咽頭癌は治療しやすいですか?
早期の急性鼻咽頭癌は治療しやすいですか?中期や後期に比べ、早期鼻咽頭がんは治療が容易であり、治癒率も...
妊婦の黄体機能不全の症状は何ですか?
子宮内膜分泌の遅延または変化によって引き起こされる黄体期の異常および子宮内膜プロゲステロン分泌の異常...
生活の中で慢性的な腰痛を引き起こす原因を探る
腰痛は主に腰に起こる痛みを指しますが、実は整形外科の一般的な疾患でもあります。では、慢性的な腰の筋肉...
胃がんの症状は何ですか?
胃がんの症状は何ですか?早期胃がんの患者のほとんどは、一般的に明らかな症状がありませんが、少数の患者...
男性の骨粗しょう症を予防するには?
男性の骨粗しょう症の予防法は何ですか?男性の骨粗しょう症を予防するにはどうすればいいでしょうか?男性...
小細胞肺がんに対するEP化学療法レジメンとは何ですか?これらの点に注意する必要がある
小細胞肺がんは、肺がんの中でも最も一般的な病理学的タイプの 1 つです。悪性度が高く、予後が悪く、骨...
肺がんにはどんな種類がありますか?
肺がんにはどんな種類がありますか?肺がんはよくあるがんです。近年、大気汚染などの要因により肺がんの発...
直腸がんの食事と維持
直腸がんの治療過程は長く、苦痛を伴い、病状が改善するためには患者は強い精神的忍耐力と十分な忍耐力も必...
鼻咽頭癌の一般的な初期症状の分析
多くの癌疾患の中でも、鼻咽頭癌は一般的な疾患です。日常生活の中で、鼻咽頭がんの初期症状について詳しく...