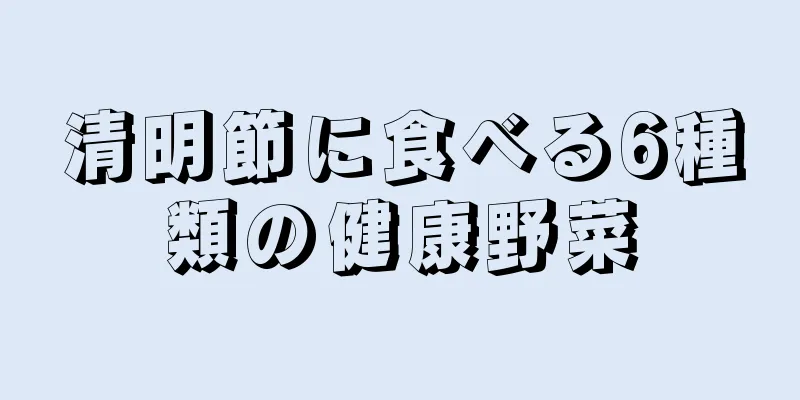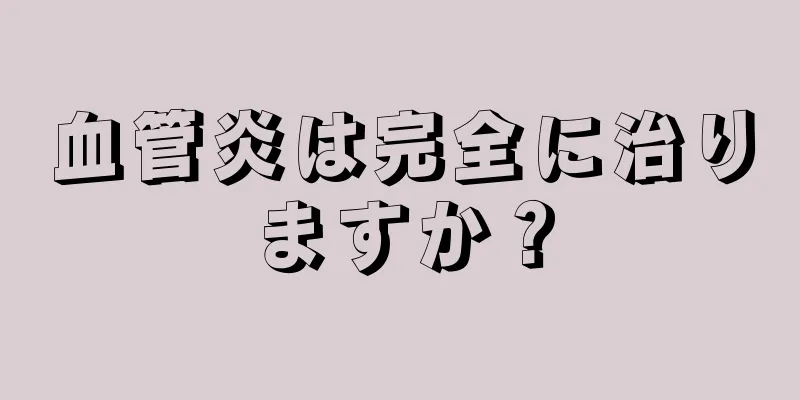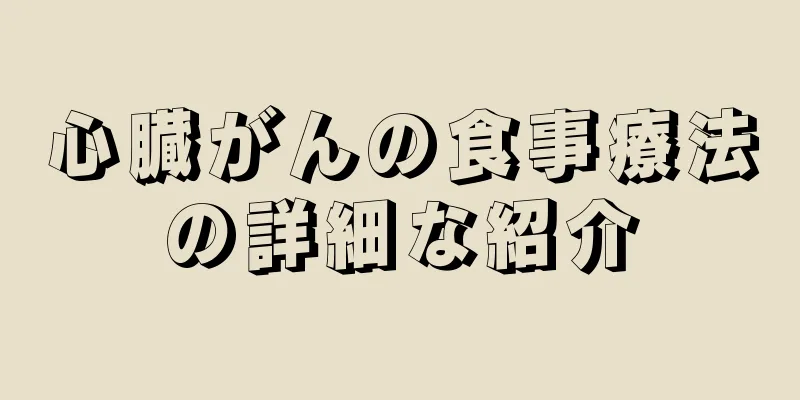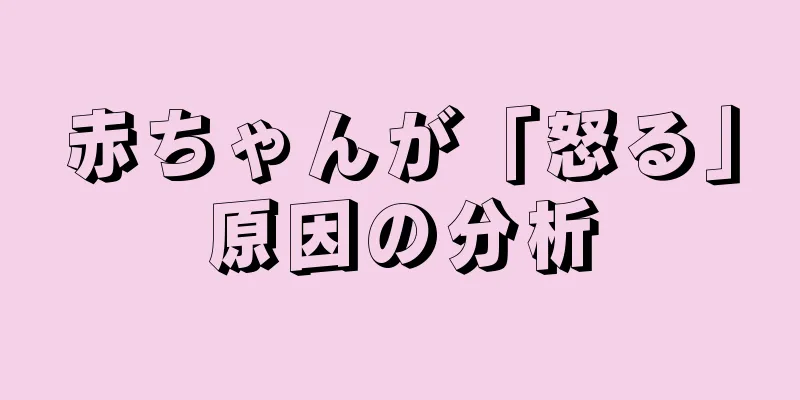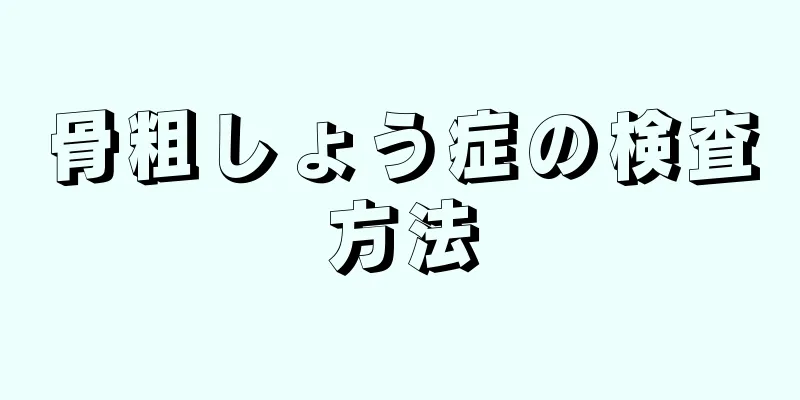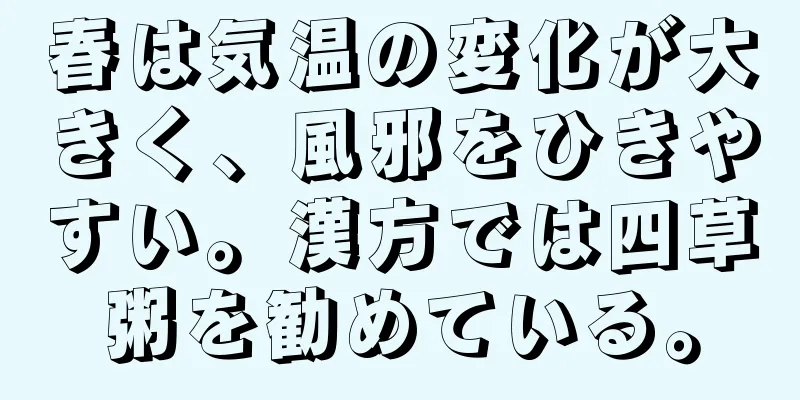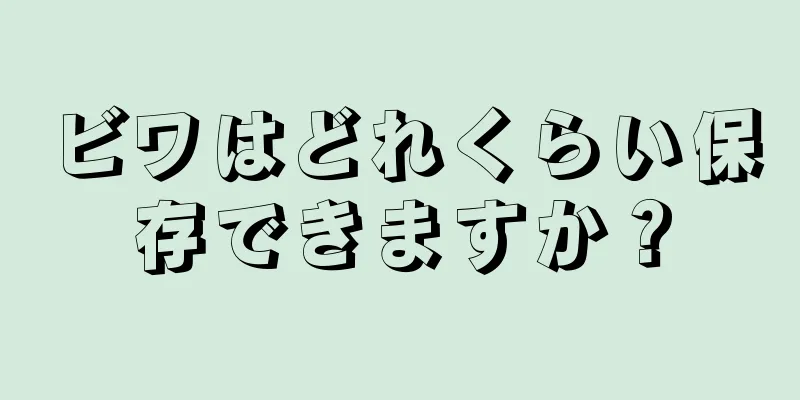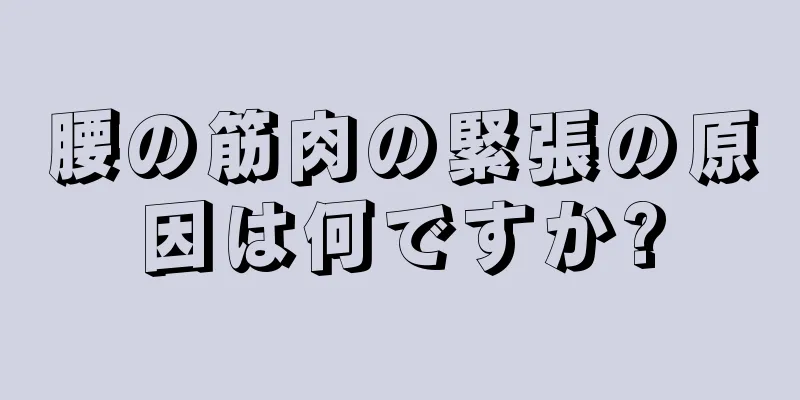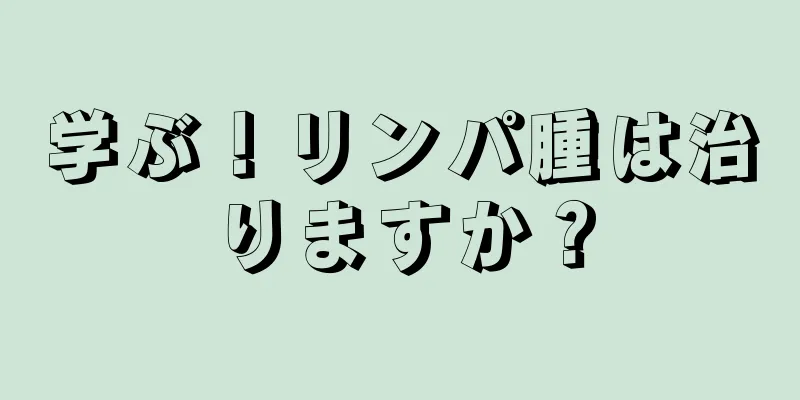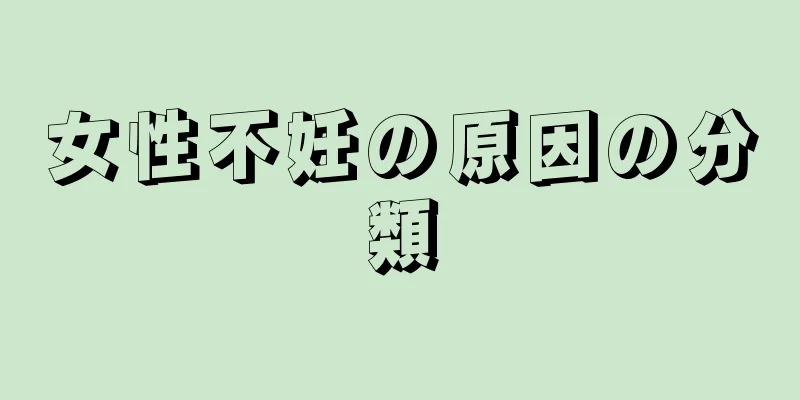動脈瘤塞栓術の注意事項は何ですか?
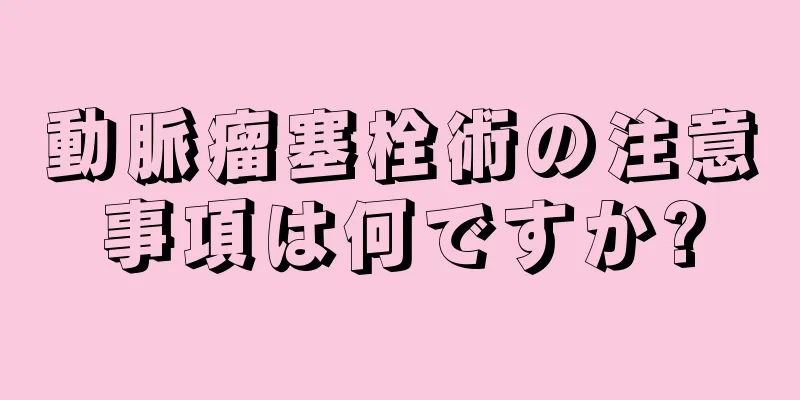
|
動脈瘤塞栓術とはどのようなものですか?注意事項は何ですか? 動脈瘤塞栓術はどうですか? バルーン整形塞栓術 1 塞栓材料:上記の材料に加えて、適切なサイズの保護バルーンを準備する必要があります。 2 塞栓ポイント:広頚動脈瘤に適用可能。塞栓には液体塞栓剤を使用する必要があります。腫瘍を有する動脈のバルーン閉塞時間は、可能な限り短縮する必要があり、通常は 1 回あたり 5 分を超えないようにします。コイル塞栓術は可能な限り密度を高くする必要があります。 ステント補助塞栓術 1 塞栓材料:上記の材料に加えて、適切なサイズの自己拡張型ステントまたはバルーン拡張型ステントを準備する必要があります。必要に応じて保護バルーンを使用してください。 2 塞栓術のポイント:広頚動脈瘤、紡錘状動脈瘤、解離性動脈瘤、動脈瘤付近の親動脈の高度狭窄などの症例に適しています。手術の前後には抗血小板薬を適切に投与する必要があります。スプリングコイルとステントが絡まないようにしてください。ステントのずれや潰れは避けなければなりません。 注意事項は何ですか? 1. 動脈瘤の理想的な塞栓術には、嚢内の密な充填が必要です。緩い塞栓術では動脈瘤の再出血を防ぐことはできません。 2. 動脈瘤が再び大きくなるのをできるだけ防ぐために、さまざまな技術とスキルを使用して動脈瘤の頸部を密に詰める必要があります。 3. 一般的な動脈瘤の場合、仮性動脈瘤と仮性動脈瘤部分を単に充填するだけでは、動脈瘤の再出血を防ぐことはできません。 4. 動脈瘤塞栓術中は、血栓症を可能な限り予防する必要があり、通常は全身抗凝固療法と同軸システムの持続注入が必要になります。 術後合併症: 1. 脳血管けいれん。 2. 血栓症。 3. 動脈瘤破裂。 4. 脳虚血。 |
推薦する
五十肩の再発を防ぐ方法
肩関節周囲炎の急性期の治療は主に薬物療法に基づきますが、回復期には再発を防ぐために局所の加温と機能強...
脊椎変形の治療における装具装着時の注意
脊柱側弯症の角度が40°以下の場合は、特殊な装具を使用して矯正および治療することができます。より良い...
舌がんの看護方法は何ですか?
現在、さまざまなメディアの発達により、人々はさまざまなメディアを通じてますます多くのことを知り、生活...
クコの実を間違った食べ方で体に害を及ぼさないように注意してください!どのような状況ではクコの実を食べてはいけないのでしょうか?
クコの実は、非常に一般的な薬用強壮剤であり、人々が日常のスープや入浴剤として好んで使う万能の食品強壮...
産後の痔出血
産後の痔の出血? 1. 出産後に痔の出血が起こった場合は、まずその部分を洗浄する必要があります。温水...
X字脚の治療にはいくらかかりますか?
X字型の脚とは、立ったときに両膝をくっつけた状態で両足を近づけることができず、両足の間の距離が1.5...
鼻咽頭がんの唾液は伝染しますか?
鼻咽頭がんは悪性腫瘍疾患であり、鼻咽頭がんのこの現象は遺伝的感受性と呼ばれています。では、鼻咽頭がん...
胃痛の予防と治療に効く5種類の薬用お粥
シトラス・オーランチウムとシランの粥材料: Citrus aurantium と Bletilla ...
曲峰火螺薬酒の効能は何ですか?
曲峰火螺薬酒の効能は何ですか?この記事は、曲峰火羅薬酒の効能と醸造法についてです。この薬酒を通じて曲...
肺がんの手術前にはどのような準備をすればよいでしょうか?肺がんの手術後の食事で注意すべきことは何ですか?
多くの肺がん患者にとって、病気の早期発見と適切なタイミングでの外科的治療が、肺がんを治療する最も直接...
人生において腰の筋肉の緊張をうまくケアすることは重要です
人生において、私たちは皆、腰の筋肉の緊張をどのようにケアすればよいかを知りたいのです。腰の筋肉の緊張...
尿路感染症を予防するには、外陰部を清潔に保つことに注意しましょう
尿路感染症に苦しむ主なグループは女性です。尿路感染症を予防するための日常的な方法はたくさんあります。...
軟部組織の損傷にはどのような運動が効果的か
軟部組織損傷は主に運動中に起こるさまざまな損傷です。傷害の部位はスポーツや特殊な技術的特徴に関連して...
五十肩の専門病院の選び方
医療技術の発展により、ますます多くの患者がその恩恵を受けています。典型的な例は、病気の治療をより的を...
生姜湯一杯で7つの病気を予防・治療できる
「冬に大根を食べ、夏に生姜を食べれば、医者に薬を処方してもらう必要がなくなる」という諺があります。古...