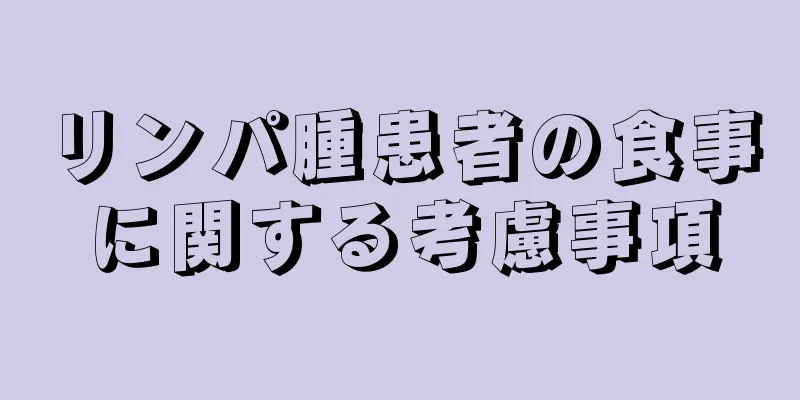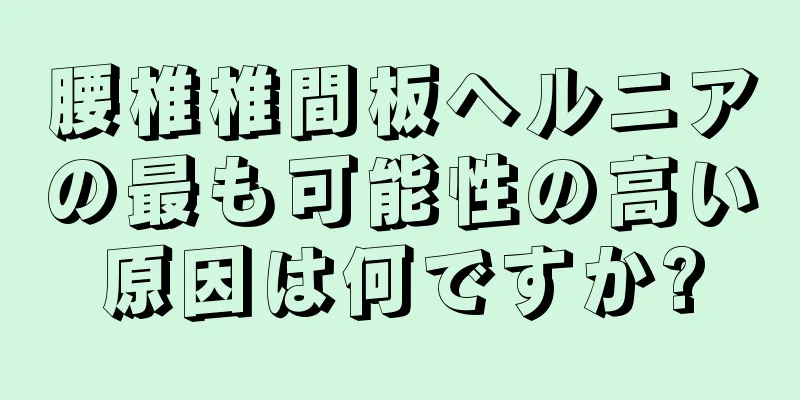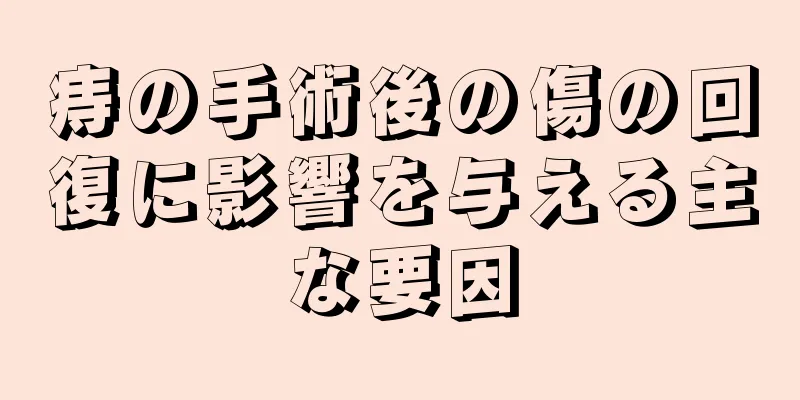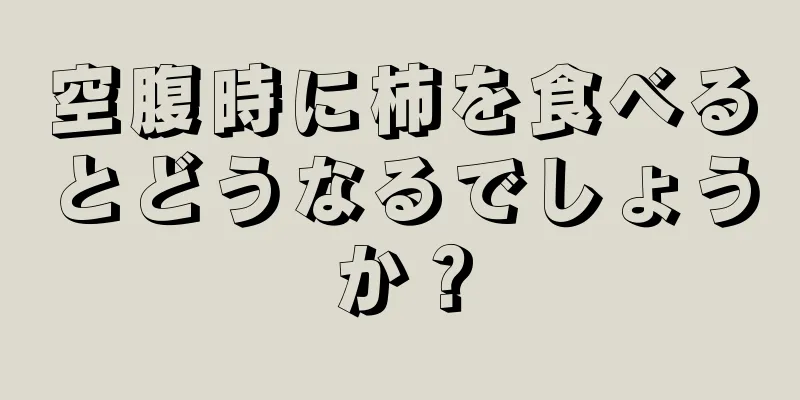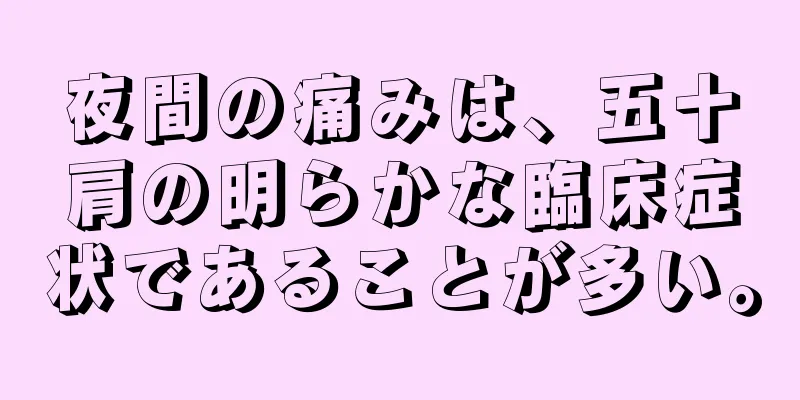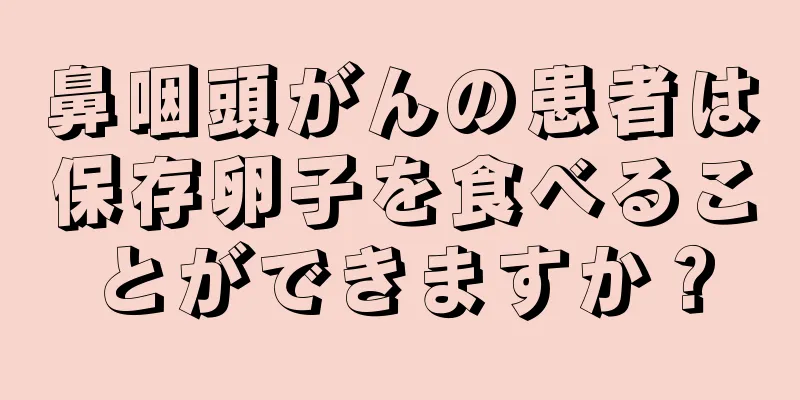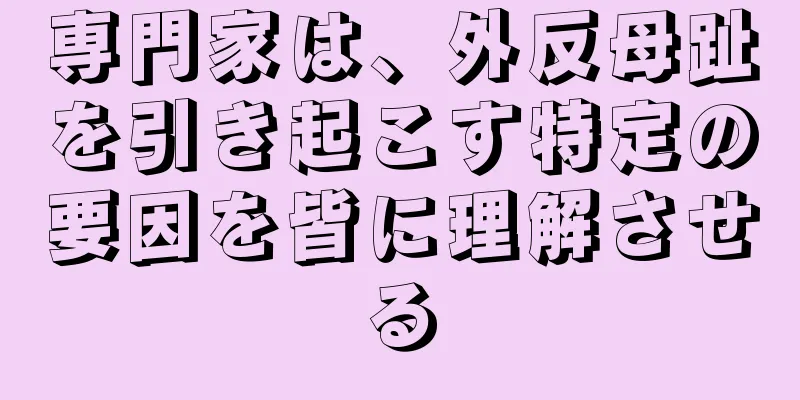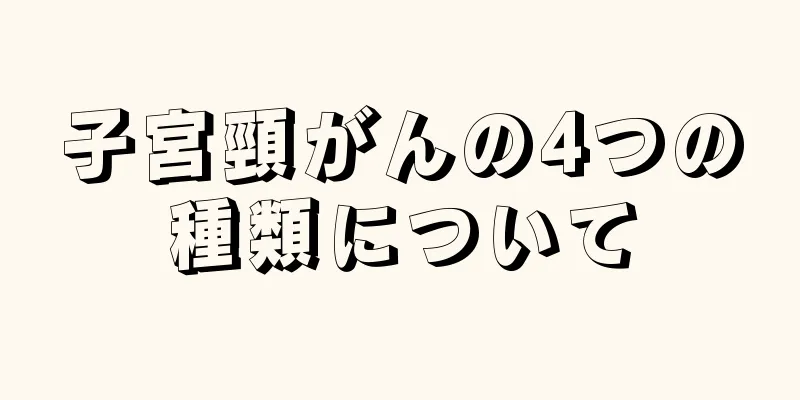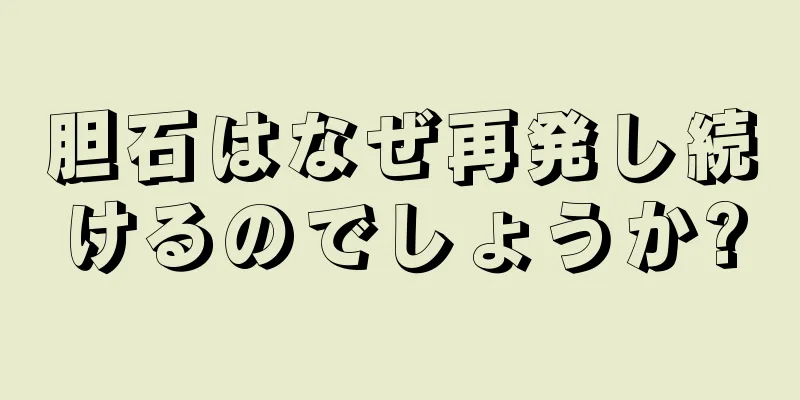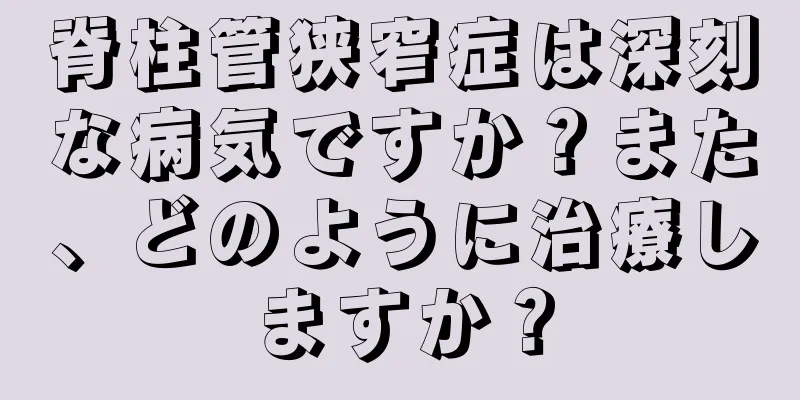前立腺がんによく使用される併用化学療法レジメン
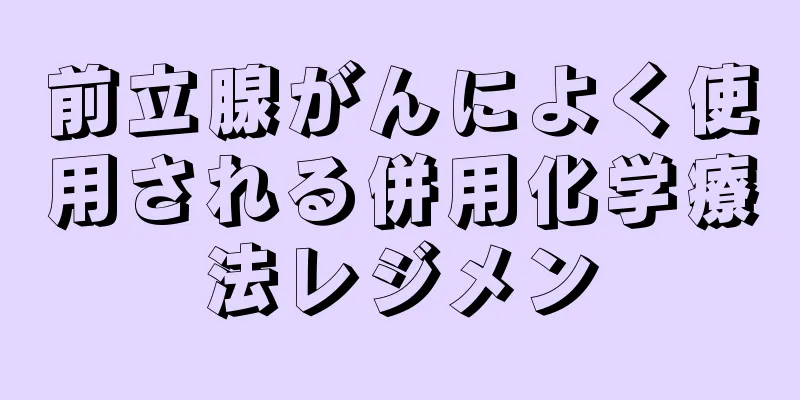
|
化学療法は前立腺がんの治療によく用いられる方法であり、その中でも単独の化学療法よりも併用化学療法の方が効果的です。現在、臨床現場で一般的に使用されている併用化学療法レジメンには、主に HHFT レジメン、CFG レジメン、HH レジメン、DGT レジメンが含まれます。 (1)HHFTスキーム ヒドロキシウレア:1~2日目に1日2回、経口で0.5g。 5-フルオロウラシル:500 mg、IV、3~6日目。 チオテパ:10 mg、IV、3~6日目。 O-アセチル化エストラジオール:10 mg、経口、3~17日目。 1 回の治療コースは 3 週間で、2 回目の治療コースは 2 ~ 3 週間の間隔を空けて実施する必要があります。 (2)CFGスキーム シクロホスファミド:400 mg、1、2、14、15 日目に IV 投与。 5-フルオロウラシル:500 mg、3、4、14、15 日目に点滴静注。 ペルクロラゾール:1日あたり体表面積1平方メートルあたり7.5gを1日目から5日目まで点滴静注します。4~5週間ごとに投薬を繰り返します。 (3)HHスキーム ヒドロキシウレア:3.5~4 g、経口、週2回。 O-アセチル化エストラジオール:10 mg、1日3回、経口投与。 1 回の治療コースは 6 週間の継続使用で、その後 2 回目のコースの前に 3 週間の休憩をとります。 (4)DGTスキーム ジエチルスチルベストロール:22~10 mg、経口、1日3回、2~3か月間。 ピペラゾール:体表面積1平方メートルあたり1日7.5g、点滴静注、1~5日目。 チオテパ:1日目から7日目まで毎日10mgを静脈内投与。 1 週間の投薬と 2 週間の休息が 1 回の治療コースとなり、3 回の治療コースを繰り返す必要があります。 ご注意:上記の投薬レジメンは、前立腺がんに対する複合化学療法レジメンです。具体的な用途は患者の状態に応じて選択する必要があります。 |
<<: 膵臓がんの治療に伝統的な中国医学を合理的に活用する方法
推薦する
ココナッツジュースの飲み方
ココナッツジュースの飲み方ココナッツの上部には3つの穴がありますが、果肉の穴は1つだけです。その穴に...
妊婦の脊椎変形に対する健康管理対策は何ですか?
脊椎変形は早期に治療するとともに、病気のコントロールのために日常の健康管理や看護にも注意を払う必要が...
ベイベリーは辛い果物ですか、それとも冷たい果物ですか?
私たちが日常よく食べるヤマモモは、性質上温かい果実で、温かい果実には唾液の分泌を促したり、喉の渇きを...
乳がんと区別すべき5つの疾患について簡単に説明します
乳がんと似た症状を示す病気は数多くあります。乳がんの見分け方を学ぶことは、病気を早期に発見するのに役...
リンパ腫とは何ですか?
悪性リンパ腫は「リンパ腫」とも呼ばれ、リンパ節やその他のリンパ組織に発生する悪性腫瘍です。これは私の...
5つの一般的な腰部軟部組織損傷の治療の概要
医学研究の継続的な進歩により、腰部軟部組織損傷の治療法が数多く登場しており、これらは腰部軟部組織損傷...
脳腫瘍のときに食べるもの
脳腫瘍は治療が非常に難しい病気です。徐々に治療する必要があります。軽く考えないでください。良くなって...
ナッツは血中脂質の調整に効果的です。食べるときは2つのポイントに注意してください
ナッツの効能と効果血中脂質の調整に役立ちます。三高症の人にとって、血圧や血中脂質を下げる薬を一日中飲...
体内の熱で唇に水ぶくれができた場合はどうすればいいですか?体内の熱を減らすための推奨食事療法
炎症による唇の水ぶくれ「怒る」というのは伝統的な中国医学における特別な用語です。喉の乾燥や痛み、目の...
ステージ2の乳がんを治療するにはどれくらいの費用がかかりますか?
ステージ2の乳がんを治療するにはどれくらいの費用がかかりますか?人々の生活水準が向上し続けるにつれて...
水腎症を早く治療するにはどうすればいいですか?水腎症を効果的に治療する4つの漢方薬
腎浮腫などの腎臓疾患が発生した場合、漢方では一般的に腎臓を温めて脾臓を強化するという原則に基づいて治...
尿道炎とは何ですか?
尿道炎はよくある病気です。近年、尿道炎の発生率は上昇し続けています。この病気はますます多くの人々の健...
ファロー四徴症はどのように診断されますか?
ファロー四徴症はどのように診断するのですか?病気の診断は比較的複雑な問題です。一般的に、より経験豊富...
乳腺炎に効く科学的食事法
病気にかかった後は患者の食生活に注意を払わなければならないことは誰もが知っています。なぜなら、良い食...
腰椎椎間板ヘルニアの6つの有用な自己検査方法
運動不足は腰椎椎間板ヘルニアの原因の一つです。そのため、腰椎椎間板ヘルニアを早期に発見できるように、...