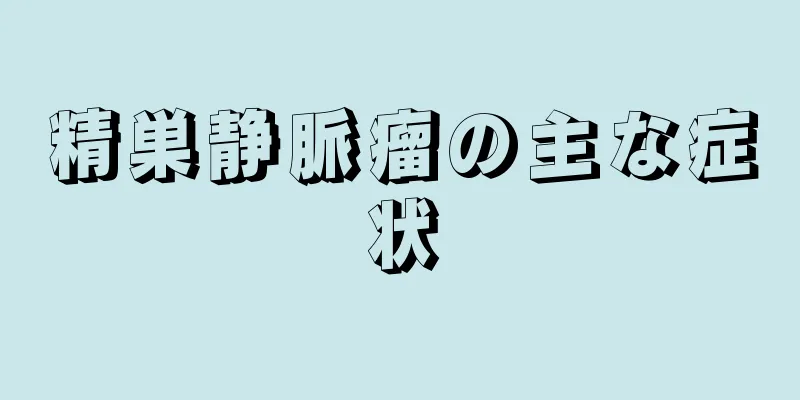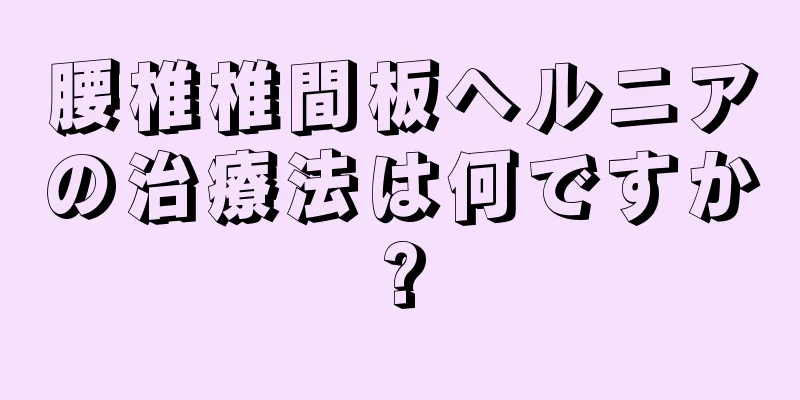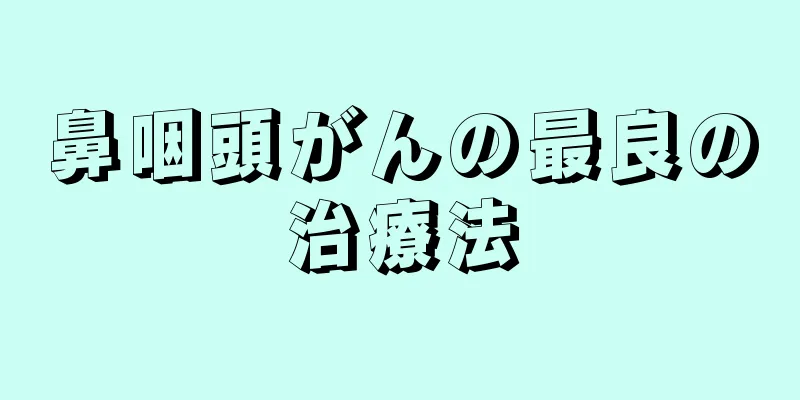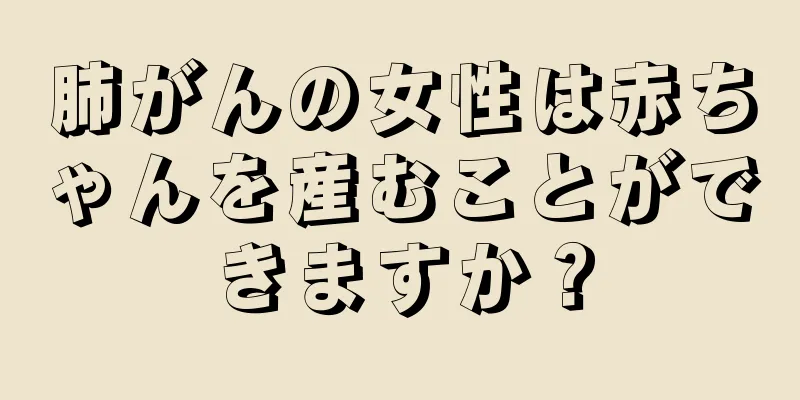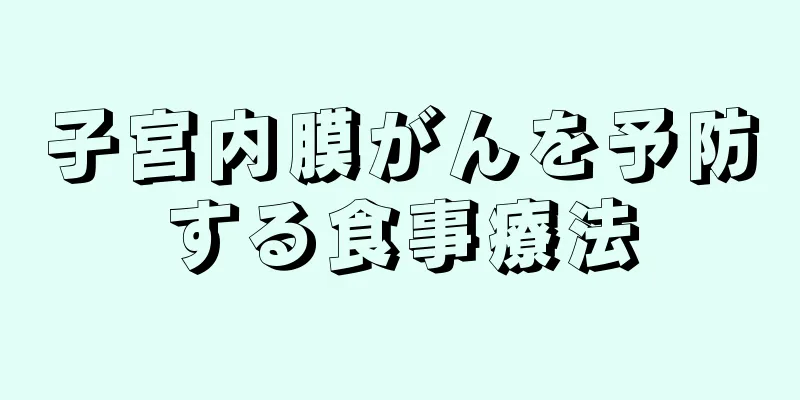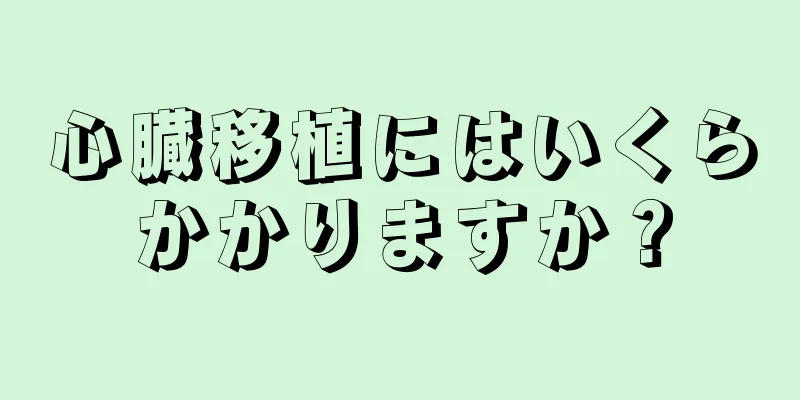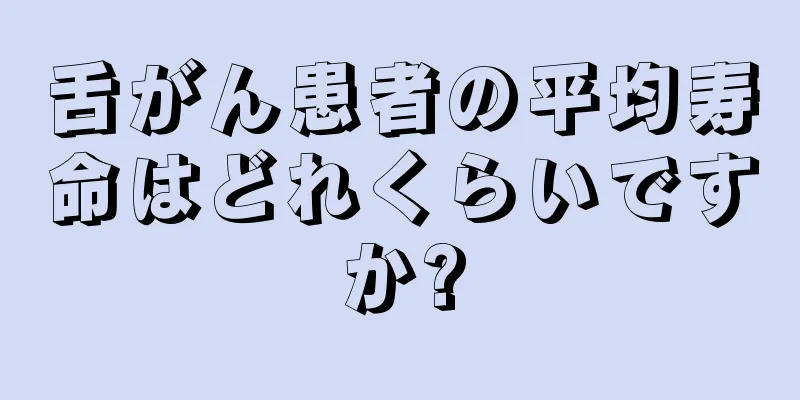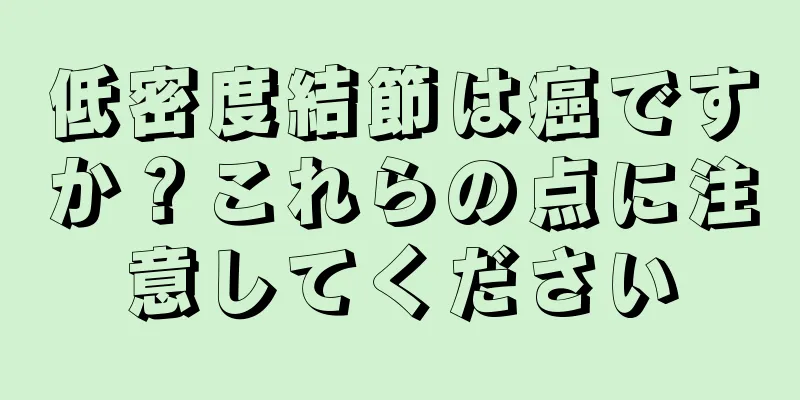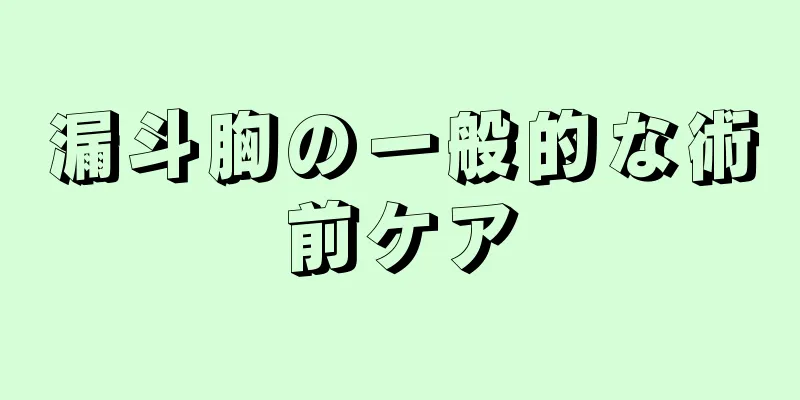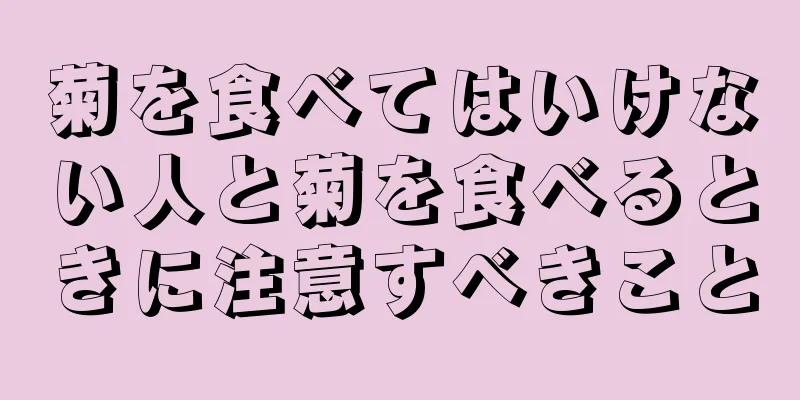下肢静脈血栓症の運動方法
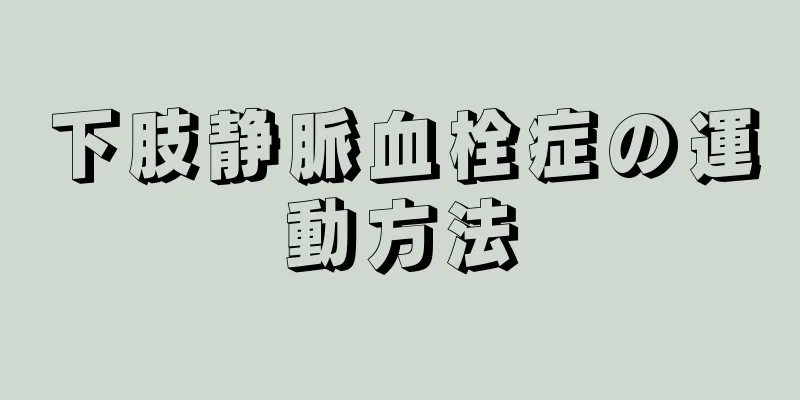
|
下肢静脈血栓症を患っている場合、どのように運動すればよいですか?人生において下肢静脈血栓症の患者が多くなる主な理由は、下肢静脈血栓症を引き起こす要因が多くあり、これらの要因が私たちによって無視されることが多いためです。例えば、運動は下肢静脈血栓症にも関係しています。では、下肢静脈血栓症を患っている場合、どのように運動すればよいのでしょうか? 運動と下肢静脈血栓症はどのように関連しているのでしょうか? 激しい運動の後にリラックスする運動をせずに突然運動を止めると、筋肉の代謝産物が時間内に消散せず、炎症や血栓を引き起こします。科学的な運動方法は、運動後徐々にリラックスし、運動と停止の間に緩衝と整理のプロセスを設けることです。ゆっくりとした動きでストレッチし、呼吸を正しく行うことで、緊張した筋肉を徐々にリラックスさせ、急速に鼓動する脈拍を遅くして正常に戻すことができ、上昇した血圧も徐々に正常に戻り、炎症の可能性を減らし、静脈血栓の形成を防ぐことができます。 全身のリラクゼーションには、上肢のリラクゼーション活動が含まれます。立ち上がって上肢を前に傾け、肩と腕を温かくなるまで繰り返し振ってください。下肢のリラックス運動:仰向けに寝て、足を持ち上げ、太ももの内側、前、後ろ、ふくらはぎの裏側、お尻、腹部、腰の横などをたたいたり、マッサージしたり、振ったりします。膝を抱えて体を丸めるリラクゼーション運動:両手で膝を抱え、しゃがみ、頭を下げ、腰椎が温かくなるまで上下に繰り返し揺らします。全身休息運動:膝を曲げ、両手を体の前で地面につけてまっすぐに立ちます。呼吸を最大限に活用し、胸に深く息を吸い込み、息を止めてゆっくりと腹部に息を吐き出します。上肢をゆっくりと上げたり立たせたりしながら、脈拍が運動前の正常な速度に戻るまでこれを数回繰り返します。 静脈血栓症の形成につながる主な要因は、血流の低下、静脈壁の損傷、血液の凝固亢進状態の 3 つです。運動選手以外にも、静脈瘤、高血糖、高血圧、脂質異常症、感染症などの患者、長時間座ったり立ったりする人、妊婦なども静脈血栓症のリスクが高くなります。これらの人々は静脈血栓症の形成を積極的に予防する必要があります。まず、長時間座ったり立ったりすることを避ける必要があります。下肢の筋肉を収縮させて弛緩させ、血液循環を促進するために、一定時間座ったり立ったりした後には散歩をするのが最適です。横になったり座ったりするときに、意識的に足をしばらく上げると静脈還流が促進されます。 2 番目のグループは静脈血栓症の高リスクグループであり、外科医、販売員、運転手、デスクワーカーなど、仕事や生活習慣により長時間座ったり立ったりする人々が含まれます。静脈血栓症を予防するために弾性ストッキングを着用することが推奨されます。第三に、高血糖、高血圧、脂質異常症の人、感染症や腫瘍の患者は、医師の指導のもと、抗凝固薬を適切な量使用する必要があります。 上記では、静脈血栓症の原因が激しい運動に関係していることを紹介しました。したがって、積極的な予防に注意を払い、静脈血栓症が重大な危険を引き起こすのを許してはなりません。 |
推薦する
嚢胞性腎がんの診断検査にはどのようなものがありますか?
腎臓がんは非常に有害な病気であることは、すでによく知られています。病気が発生すると、しこりができ、患...
卵巣がん手術後の卵巣を養う食事療法
卵巣がんは女性の健康に極めて有害で、死亡率が非常に高い悪性腫瘍です。卵巣がんの手術後、患者の気血は不...
新生児くる病の主な原因
「新生児のくる病の原因は何ですか?」多くの人がこの疑問を抱いているに違いありません。くる病はよくある...
椎間板自体の弱さも腰椎椎間板ヘルニアの原因となる。
腰椎椎間板ヘルニアは患者の日常生活に深刻な影響を及ぼします。実際、誰もが日常生活の中で腰椎椎間板ヘル...
子宮がんの初期段階の治療方法
がんは人々が恐れる病気であり、治療も難しい病気です。子宮がんは一般的な婦人科疾患の一つです。子宮がん...
専門家が前立腺がん診断のポイントを解説
前立腺がんは、男性の健康全般に深刻な影響を及ぼす悪性腫瘍であり、男性の主な死因となっています。では、...
胆石の再発を防ぐ方法
胆石の再発を予防するには、食生活の調整、適度な運動、良好な生活習慣の維持など、さまざまな面で注意が必...
卵管閉塞には手術が必要ですか?
卵管閉塞の治療には手術が必要ですか? 不妊症は多くの家族にとっての懸念事項です。他の家族が家族の幸せ...
乳房結節の治療に最も有名な病院を選ぶにはどうすればいいですか?
乳房肥大など乳房疾患は数多くあります。乳房の過形成により、患者は痛みの症状や乳房結節であるしこりを経...
脳形成異常による水頭症患者に対する食事療法
脳形成異常による水頭症などの病気の治療に加えて、患者の食事管理も非常に重要な側面です。あなたの症状に...
血管炎になったとき、食事で何に注意すればよいですか?
血管炎のときはどのような食事に注意すればよいでしょうか?病気にかかった後は食生活に注意しなければなり...
扁平足は栄養にも関係している
扁平足は栄養とも関係があります。一般的に、栄養失調が扁平足の最も明らかな原因です。では、扁平足の他の...
骨粗しょう症を予防する最も重要な方法
人生において骨粗鬆症に悩まされる人はたくさんいますが、その予防方法を知らない人もたくさんいます。次に...
舌がんかどうかを見分ける方法
口腔内の変化を観察し、痛みや不快感に注意し、機能障害を確認し、首のしこりに注意し、全身症状に注意する...
進行した大腸がんの治療方法
大腸がんは悪性腫瘍の中でも頻度の高いものの一つで、その発生率は悪性腫瘍の中で4~6位にランクされてい...